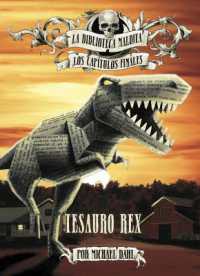出版社内容情報
はじめて明らかにされる家飲みの歴史。いつ頃から始まったのか? 飲まれていた酒は? つまみは? 著者独自の酒の肴にもなる学術書、第四弾!
内容説明
万葉の昔からはじまり、江戸時代に花開いた日本人の家飲み。当初健康のため、安眠のために飲まれていた「寝酒」は、灯火の発達とともにゆっくり夜を楽しむ「内呑み」へと変わっていく。飲まれていたのは濁酒や清酒、焼酎とみりんをあわせた「本直し」等。肴は枝豆から刺身、鍋と、現代と変わらぬ多彩さ。しかも、振り売りが発達していた江戸の町では、自分で支度しなくても、家に居ながらにして肴を入手することができた。さらに燗酒を売る振り売りまでいたため、家に熱源がなくても燗酒が楽しめた。驚くほど豊かだった日本人の家飲みの歴史を繙く。
目次
序章 酒は百薬の長
第1章 万葉集に詠まれた独り酒
第2章 中世の独り酒
第3章 晩酌のはじまり
第4章 明かりの灯る生活
第5章 灯火のもとでの外食
第6章 江戸庶民の夜間の暮らし
第7章 江戸で花開いた晩酌文化
第8章 晩酌の習慣が広まる
第9章 多彩な晩酌の肴
第10章 長くなった夜の生活時間
著者等紹介
飯野亮一[イイノリョウイチ]
食文化史研究家。服部栄養専門学校理事・講師。早稲田大学第二文学部英文学専攻卒業。明治大学文学部史学地理学科卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
37
万葉から江戸時代あたりまで、昔日本の晩酌文化を掘り起こし。①かの時代、「晩酌」と言う言葉はなく「寝酒」と称されていた。②江戸の世の酒は燗酒がスタンダード。③当時の酒は、超辛口で暖めることによって飲みやすくなった。④夕方、河岸に上がった鯵が棒振りのによってその日の晩酌のつまみになる等江戸版テイク・アウトつまみがことのほか充実、等々。飲み会で語れるウンチク話し多数。同時掲載の多数の挿画、人々の表情が活き活きでこれだけ眺めていても楽しめる。2024/04/25
グラコロ
30
たとえコンビニやウーバーイーツや出前館がなくっても、振り売りから買った材料でネギマを小鍋立てにして一杯やったり、屋台で買った天ぷらや煮しめで一杯やったり、時には豪勢に仕出し屋に頼んだ刺身盛り合わせで一杯やったり。でも寒い季節に売りに来るおでん燗酒が一番。ああ、江戸時代にタイムスリップしたい!2024/01/10
ジュンジュン
15
読みやすさと豊富な図版でシリーズ第四弾。テレビもラジオもスマホもない江戸時代。庶民が一日働いて、家に帰って限られた時間の中で飲む酒は今日の我々以上に大きな意味を持っていた。そして、一生懸命働きさえすれば、酒も買えたし、肴は手に入った(355p)。テイクアウトあり、デリバリーありと意外と充実の晩酌文化を多方面から紹介する。2024/07/09
いとう・しんご
13
読友さんきっかけの食いしん坊シリーズ。風呂上がりの発泡酒、プッシュ~~が大好きな私には生唾ゴックン、たまらない一冊でした。江戸時代にお煮染め屋さんが材料ごとに煮汁を買えて売っていたとか、江戸と上方の味付けの違いが当時から知られていたとか、やっぱ日本人の味覚って繊細だったんだなぁ、と感心しました。2024/06/13
pushuca
11
万葉の昔から晩酌は存在し、それが江戸期に鼻開いた様子が描かれている。夜が明るくなったからだ。肴の豊富さは、現代以上なのではなかろうか?2024/01/31
-
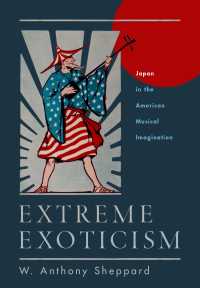
- 洋書電子書籍
-
アメリカ音楽と想像の日本
Ext…