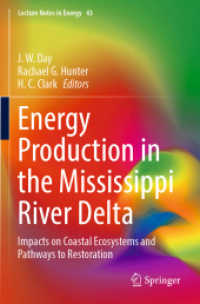出版社内容情報
百姓たちは自らの土地を所有し、織物や酒を生産・販売していた――庶民の活力にみちた前期資本主義社会として、江戸時代を読み直す。解説 荒木田岳
===
江戸時代の日本について、鎖国によって孤立し停滞した封建制社会であったと受け止める傾向がある。また、農民や町人は、厳しい身分制度でがんじがらめの支配を受けていたと信じられがちである。しかし村々に残る資料をみて歩くと、この時代の百姓たちは自ら所有する土地を耕しながら布や酒をつくって店をひらき、さらには寄合の協議で村の運営を動かすこともあったことなどが分かってくる。江戸時代はむしろ、元気な百姓が主役の、近代的な前期資本主義社会だったのだ。支配者史観を覆し、庶民の視点から江戸時代の歴史を読みなおす。 解説 荒木田岳
===
「身分に縛られた暗い封建社会」は本当か?
百姓たちは元気だった!
===
【目次】
はしがき
序章 「日本近世史」のあやうさ
1 制度はどこから生まれたか/2 暗記学になった「近世史」/3 歴史を語らない法と制度/4 歴史の主役は百姓
第一章 百姓を独立させた検地
1 名主と名子の身分制/2 大開発時代の原動力/3 時代転換のキーワード
第二章 身分社会の終焉
1 士・農・工・商は職分/2 家をめぐる身分の消滅/3 大家族から世帯へ
第三章 法と制度のからくり
1 支配者史観の落とし穴/2 編纂された法典/3 分地制限令の背景
第四章 新しい社会の秩序
1 時代の主催者としての百姓/2 団結と秩序/3 村の総意で選ばれた名主/4 村の掟/5 村八分
第五章 百姓の元気
1 はげしい農産物需要/2 自給自足説の失敗/3 百姓の成立と展開/4 無高百姓の出現
第六章 民意が公論となるとき
1 奉行罷免の要求/2 契約としての定免制/3 百姓一揆の思想/4 とりやめになった新田検地
第七章 村に学んだ幕閣
1 国産自給論と交易論/2 輸出解禁/3 空転する国益論/4 専売機関の挫折/5 村にできた工場
文庫版解説 荒木田岳
内容説明
江戸時代の日本について、鎖国によって孤立し停滞した封建制社会であったと受け止める傾向がある。また、農民や町人は、厳しい身分制度でがんじがらめの支配を受けていたと信じられがちである。しかし村々に残る資料をみて歩くと、この時代の百姓たちは自ら所有する土地を耕しながら布や酒をつくって店をひらき、さらには寄合の協議で村の運営を動かすこともあったことなどが分かってくる。江戸時代はむしろ、元気な百姓が主役の、近代的な前期資本主義社会だったのだ。支配者史観を覆し、庶民の視点から江戸時代の歴史を読みなおす。
目次
序章 「日本近世史」のあやうさ
第1章 百姓を独立させた検地
第2章 身分社会の終焉
第3章 法と制度のからくり
第4章 新しい社会の秩序
第5章 百姓の元気
第6章 民意が公論となるとき
第7章 村に学んだ幕閣
著者等紹介
田中圭一[タナカケイイチ]
1931‐2018年。新潟県佐渡郡金井町生まれ。新潟大学人文学部経済学科卒業。高校教諭を経て、67年京都大学国内留学、88年筑波大学教授、94年群馬県立女子大学教授などを歴任。従来の、武士を中心とした「日本近世史」の史観に異議を唱え、当時の一般庶民である百姓こそが時代の主役であったという視点を、村々に残る史料をひもときながら主張しつづけた。著書に『佐渡金銀山の史的研究』(刀水書房、第9回角川源義賞)、『帳箱の中の江戸時代史』(刀水書房、新潟日報文化賞)、『日本の江戸時代』(刀水書房)ほか多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
HONEY
Go Extreme