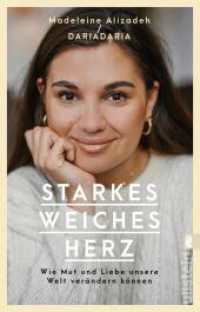出版社内容情報
江戸時代、天文学者たちは星を見上げ、暦に命を懸けた。
鎖国下の日本で外国の知識やことばと必死で格闘し、
研究に身を捧げた人びとを描く情熱の天文学史。
・渋川春海による「日本独自の暦」を作る苦闘
・西洋天文学の導入を目指した徳川吉宗と麻田剛立
・地動説、彗星、星座は当時どう考えられていたか?
・伊能忠敬の全国測量異聞――幻となった間重富の測量計画
・オランダ語を独力で習得し、命がけで「ラランデ暦書」を翻訳
・最新情報を求めシーボルト事件で獄死した高橋景保 etc.
現役の科学館学芸員である著者が、江戸時代の天文学者たちの思索と、
ドラマにあふれた人生をたどる。待望の増補文庫化!
解説 渡部潤一
装画 平岡瞳/装丁 小川恵子(瀬戸内デザイン)
内容説明
日本の天文学の大転換は江戸時代に起こった。日本独自の暦を初めて作った渋川春海、西洋天文学の導入を目指した徳川吉宗と麻田剛立、全国の測量で名を馳せた伊能忠敬、地動説に取り組んだ高橋至時、最新情報を求めシーボルト事件で獄死した高橋景保…。先行するヨーロッパや中国の書物と格闘し研究に身を捧げた天文学者たちの思索と、ドラマにあふれた人生をたどる。
目次
プロローグ 天文と暦―日本の天文学ことはじめ
第1章 中国天文学からの出発―渋川春海の大仕事
第2章 西洋天文学の導入―徳川吉宗・麻田剛立が開いた扉
第3章 改暦・翻訳・地動説―高橋至時・伊能忠敬による発展
第4章 変わる天文方の仕事―間重富・高橋景保の奮闘
第5章 西洋と東洋のはざまで―江戸の天文学の完成期
補章 書物と西洋天文学
著者等紹介
嘉数次人[カズツグト]
1965年生まれ。大阪教育大学大学院教育学研究科修了。1990年より大阪市立科学館学芸員。学芸課長。近世日本の天文学を中心とした科学史と科学普及を専門としている。本書『天文学者たちの江戸時代』(ちくま新書、2016年)が初の単著(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
やいっち
DK-2084
甘コロリ
Steppenwolf