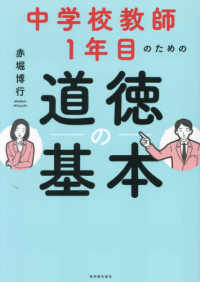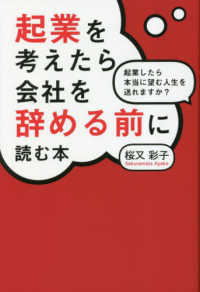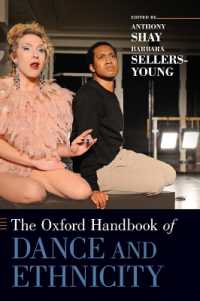出版社内容情報
古本ライター、書評家として四半世紀分の古本仕事の集大成。書籍未収録原稿や書き下ろしも多数収録したベスト・オブ・古本エッセイ集。
内容説明
買って、読んで、書いてきた。ライター、書評家として、四半世紀分の古本仕事の集大成。古本屋のお作法と流儀。ブックオフやネット販売の登場、女子の古本屋、中央線新世代古本屋の活躍、そして、突然のコロナ騒動まで。古本を愛しすぎる著者だからこそ書ける業界の変化と動向のあれこれ。出版コラム「愛書狂」など単行本未収録原稿も多数収録した文庫オリジナルのベスト・オブ・古本エッセイ集。
目次
第1章 古本屋と古本のお作法(買った本、全部読むんですか?;古本屋の作法指南 ほか)
第2章 古本ワンダーランド(トウキョウのブローティガン釣り;ぼくたちにはこの“大きさ”が必要なんだ ほか)
第3章 古本と私―大阪・京都・東京(均一小僧;古雑誌という砂糖の山 ほか)
第4章 愛書狂―二〇〇八年から二〇二三年の本の話(蟹工船ブーム;重い本・厚い本 ほか)
第5章 古本屋見聞録(私の古本屋体験記;古本屋という職業 ほか)
著者等紹介
岡崎武志[オカザキタケシ]
1957年大阪府生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町ライター」などの異名でも知られる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
68
著者の古本に関するエッセイ集成。筑摩から出た本を纏めた物なので重複注意。いやホント古本に纏わる文章って読んでいるだけで心が豊かになる気がするなあ。内容は著者の古本彷徨記から古本屋指南、買った本に纏わるアレコレや2008年から2023年までの出版界古本界隈の動向等となっている。『蟹工船』ブームとかあったなあ。とあれ隅から隅まで古本愛のたっぷり詰まった本なので、古本者だけではなく読書に関心のある人間なら是非とも読むべき一冊だと思う。私も読んでいるとまたあちこちの古本屋、古本市を訪ね歩きたくなるなあ。2024/03/03
tamami
62
還暦を大分回った著者の、古本に関する文章の集大成。著者幼少の砌から現在に到るまで、古本に捧げられた人生を様々に記す。古本探求の昔と今、古本屋さんでの本人との出会い、印象に残る作家や作品等々、古本を巡る表話や裏話がびっしりと420頁余。第一章、古本屋と古本のお作法、では初心者向け?に古本道入門ともいうべき事柄が記され、第二章、古本ワンダーランドでは著者の古本を巡る体験談が語られる。以下第五章まで、古今、硬派から軟派まで、沢山の本が紹介されているので、読者としては一冊でも二冊でも、琴線に触れる本があれば幸い。2024/01/27
へくとぱすかる
54
街の話について、208ページの谷川さんの発言というのは、おそらく小室等23区コンサートでゲストとして話された内容だろう。レコードにも収録されている。話題が古本だけに、それぞれがうなずいたり笑ったりしながら楽しく読んだ。著者の自伝的な話は、さすがに悲壮でシリアスな事柄もあったが、それでも本との付き合いは大きく今に至る流れとなって続いていく。古本の話題でありながら、これ全体がまさに著者の自伝と言ってもいいくらいだ。ちょうど著者自身が書いているように、できあがった本棚自体がひとつの創作であるのと同じなのだろう。2024/01/20
つちのこ
46
古本にまつわるウンチクが凄い。まさに古本マイスターといってもいい存在。未収録エッセイを除き、これまでの著作を再編集している点で新鮮さはないが、膨大な原稿をジャンル別、年代別に編集し、多角的に古本全般を論じた視点が面白い。古本を愛してやまない姿勢が十分すぎるほど伝わってくる。時代とともに斜陽する古本業界への危惧に反して、需要がある以上、根強いマニアの存在は不変のようだ。古本が詰め込まれた本棚に挟まれるように立つ、著者のカバー写真には得体のしれないオーラが漂う。本の雑誌の『絶景本棚』にぜひ取り上げて欲しい。2024/08/18
kazuさん
39
古本屋と普通の書店の違いが語られる。古本屋では、陳列されている本は店主がすべて買い取り、独自の視点で並べられている。売りたい本は目立つように、客の目線の高さに収納される。客は、店の引き戸を静かに丁寧に開けることから気をつけ、店主に商品である本を拝見させていただくという態度で店内を歩かなければならない。カップルでの入店は御法度、値引き交渉は厳禁、本は丁寧に扱い、読んだら元の場所に戻すなどのルールに従う。古本屋を訪れる際の心構えに関する記述が特に印象に残った。2024/03/28