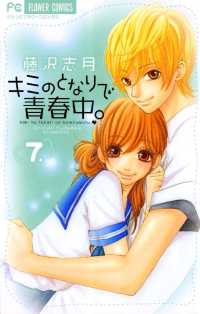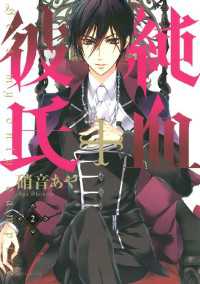出版社内容情報
江戸二六〇年の間、変わり続けた女たちのファッション。着物の模様、帯の結び、髪形、装身具など、その流行の変遷をカラーイラストで紹介する。
徳川260年の間、江戸の女たちは装うために、チャレンジを続けた。江戸初期の武家婦人の晴れ着は重厚で豪華な衣装。一方、庶民は自分で手作りという時代。やがて、江戸中期になると色彩豊かで優美な世界が町方の富裕層のなかから生まれ出る。そして江戸後期は、「粋」で個性的な時代へと変化する。江戸の女たちの着物、髪形、化粧などを紹介する、服飾カラー大全。見て楽しい、読んで役に立つ。
装うことに目覚めた女たち!
プロの仕事にも役に立つ!
服飾カラー大全
内容説明
徳川260年の間、江戸の女たちは装うために、チャレンジを続けた。江戸初期の武家婦人の晴れ着は重厚で豪華な衣装。一方、庶民は自分で手作りという時代。やがて、江戸中期になると色彩豊かで優美な世界が町方の富裕層のなかから生まれ出る。そして江戸後期は、「粋」で個性的な時代へと変化する。江戸の女たちの着物、髪形、化粧などを紹介する、服飾カラー大全。見て楽しい、読んで役に立つ。
目次
1 江戸時代
2 初期 工芸服の武家婦人と手作り麻衣の庶民
3 中期 上層町方の女小袖
4 後期 武家女小袖
5 後期 町方女の着物
6 化粧と女の髪形
7 補助衣料
8 四季の装いと成長儀礼
著者等紹介
菊地ひと美[キクチヒトミ]
衣装デザイナーを経て、早稲田大学の一般講座や江戸東京博物館で10年間学びつつ、著作活動(文と絵)に入る。2002年から始まった日本橋再開発に作品が起用された。また、2004年国立劇場より制作依頼を受けて描いた『伝統芸能絵巻』全4巻(10メートル)は、海外2カ国の国立美術館(ローマ・ブタペスト)で3カ月間展覧された。2008年には、丸善・丸の内本店にて同絵巻の国内初披露を含む個展を開催。現在は絵本を含む著作執筆を中心に活動中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。