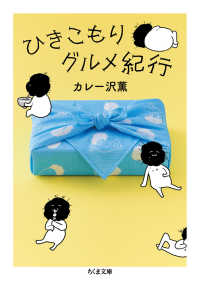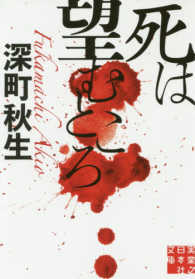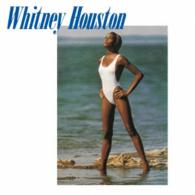出版社内容情報
昭和の名人から談志、志ん朝、また、現役トップの演者は「古典落語」の演目をどう演じてきたか。画期的落語論待望の文庫化。追加三演目を書下ろし。
内容説明
同じ「芝浜」は一つとしてない。志ん生、文楽、圓生ら昭和の名人から、志ん朝、談志、さらには小三治、談春、一之輔など現役トップの落語家まで、彼らは「古典落語」の代表的演目を分析し、アレンジを加え、ときに解体もしながら、どう演じてきたのか。演目の進化から落語の“本質”に迫る、画期的落語評論。文庫化にあたり、「死神」「居残り佐平次」「子別れ」についての書き下ろしを増補。
目次
第1章 芝浜(耳で聴く文学作品―三木助;ドラマティックな感情の注入―談志 ほか)
第2章 富久(愛すべき幇間―文楽;効果的な第三者目線―志ん生 ほか)
第3章 紺屋高尾と幾代餅(瓶のぞきの後日談―圓生;ロマンティックな恋―談志 ほか)
第4章 文七元結(テキストとしての速記―圓朝;演劇的リアリズムの誕生―圓生 ほか)
著者等紹介
広瀬和生[ヒロセカズオ]
1960年、埼玉県生まれ。東京大学工学部卒。ヘヴィメタル専門誌「BURRN!」編集長、落語評論家。1970年代からの落語ファンで、ほぼ毎日、生の高座に接し、自ら落語会のプロデュースも手掛ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
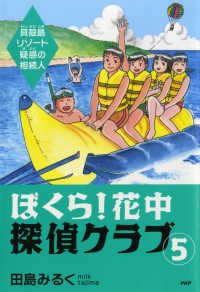
- 電子書籍
- ぼくら!花中探偵クラブ 5 - 貝殻島…