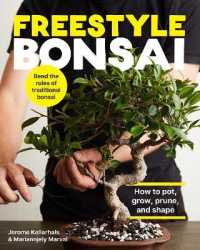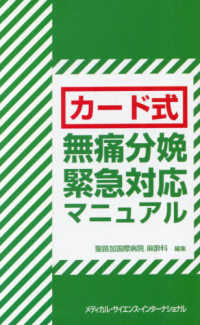出版社内容情報
カレー、トンカツからテーブルマナーまで――日本人は如何にして西洋食を取り入れ、独自の食文化として育て上げたのかを解き明かす。解説 阿古真理
内容説明
トンカツ、コロッケ、ライスカレーの発明、戦争が需要を増大させた牛肉・豚肉、白くて気味悪がられた西洋野菜・白菜、数々の文豪を虜にしたアイスクリーム、明治天皇と福沢諭吉がPRに一役買った牛乳―。素材・料理法からテーブルマナー、はては食堂車まで、日本人は如何にして西洋食を取り入れ、日本独自の食文化「洋食」として育て上げたのか。
目次
西洋料理事始
西洋食作法
牛肉ノススメ
カツレツ記、トンカツ記
コロッケ秘録
ライスカレー白書
ジャパニーズ・ハイカラ・ソース
西洋野菜指南
パンの手帖
コーヒー狂想曲
長い長い牛乳のあゆみ
アイスクリームの時代
ラムネ伝説
食堂車見聞録
「にっぽん洋食」の底力
著者等紹介
小菅桂子[コスゲケイコ]
1933‐2005。東京都生まれ。昭和女子大学短期大学部国文学科卒業後、國學院大学文学部卒業。くらしき作陽大学食文化学部教授を務めた。専門は食文化史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
54
ハヤシライスは、ハヤシさんが考案したものなのか……!2018/01/05
コジ
34
元々は西洋野菜だった白菜。ラムネの語源はレモネード。本書にはこの他沢山の洋食知識が満載。三大洋食と言っても過言ではないトンカツ、コロッケ、ライスカレーなど馴染み深い料理一つ一つにスポット当てて解説してくれている点も好印象。当初洋食オンリーのメニューだった鉄道の食堂車を取り上げたのも面白い。「和洋折衷料理」の言葉にあるように、過去様々な人々の知恵と努力によって今日の洋食がある。今や和食が海外で評価される時代、海外のナンチャッテ和食もその国の人々の口に合うように工夫された賜物と思えば安易に笑えなくなる。2017/09/28
❁Lei❁
31
洋食誕生の秘密に迫った、読んでいるだけでお腹が空いてくる本。牛鍋やカツレツ、コロッケなどの当時のレシピが引用されていて、とにかく美味しそうです。ソースをどばどばかけたカツレツなんて、想像するだけでよだれが……。また、アイスクリンとアイスクリームが別物だと知ってびっくりしました。昔ながらの素朴なアイスクリン(シャリシャリしているらしい)は、なんと高知で味わえるそうです。さらに、アイスに添えられているウエハースの歴史にまで言及されており、とても興味深かったです。飽くなき食への探究心が発揮されている一冊です。2025/08/27
澤水月
11
食べ物初めてモノ大好き。今ある近現代食の歴史、多くの文献の参照元(文庫→電書も)。いつもどこかを読みながら食事してた。やはり「表立っての」肉食エピどれも面白すぎる。日本人向け食肉始まりは横浜、“まず汚れなきよう青竹四本立ててそれに御幣を結び、四方へしめ縄を張ってその中に牛をつなぎ、掛矢、つまり木の大槌で牛をなぐり殺した”。西洋野菜、ソースの普及など文献と当事者インタで多く網羅。日本の食堂車をこき下ろす箇所だけ「?」。読了6/182024/06/21
ハルバル
11
偶然個人的なダイエットとコロナ禍が重なり、食生活の見直しをしたり健康について考えることが増え、その延長で食文化に興味が湧いてきた次第。現在では当たり前のように食べられている洋食が明治期以来、どのような試行錯誤を経て日本の食卓に根付いていったかをエッセイ形式で書いた食文化史のパイオニアにして決定版。有名な木村屋のあんパンも、みんな大好きなカツ丼もオムライスもハヤシライスだって日本人が洋食を身近にしようと和洋折衷の末に作り上げたものだったのだ。美味しいものを好きなだけ食べられる平和な時が早く訪れますように。2020/05/16