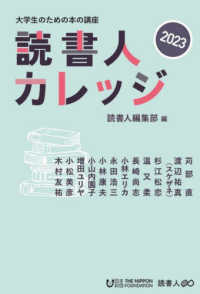出版社内容情報
名古屋中村遊廓跡で出くわした建物取壊し。そこから著者の遊廓をめぐる探訪が始まる。女たちの隠された歴史が問いかけるものとは。解説 井上理津子
神崎 宣武[カンザキ ノリタケ]
内容説明
ある日、名古屋駅裏を歩いていた著者は、一軒の建物が取り壊されようとしている場に出くわす。それが中村遊廓の成駒屋だった。その場に残された家財道具を手掛かりに、著者は遊廓の実像を求めて、多くの人から聞取りを始める。大正から昭和の隆盛期、さらには売春防止法以後の関係者たちはどう生きていったのか。読書史上に残る名著文庫化。
目次
序章 名古屋中村「新金波」にて
1章 中村遊廓との遭遇(遊廓を知らない世代のロマン;名古屋駅裏の猥雑さ;巨大な遊廓建築の群 ほか)
2章 道具からみた「成駒屋」(玄関まわりの風景;客引きの呼吸;帳場に残っていた『花山帳』から ほか)
3章 娼妓たちの人生(無理強いができない;松山の居酒屋で;娼妓たちの家庭環境 ほか)
終章 遊廓の終焉
著者等紹介
神崎宣武[カンザキノリタケ]
1944年岡山県生まれ。民俗学者。武蔵野美術大学在学中より宮本常一の教えを受ける。長年にわたり国内外の民俗調査・研究に取り組むとともに、陶磁器や民具、食文化、旅文化、盛り場など幅広いテーマで執筆活動を行なっている。現在、旅の文化研究所所長。郷里で神主も務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のんすけ
37
この本は30年前に書かれた著書の文庫化であり、本に出てくる証言もすでに古くなってしまっている。それだからこそ残ったものなんだろうと思う。名古屋市中村区にそんなに大きな色街があったことを、愛知県民でも知らなかった。確かに名駅の裏側は今でも猥雑で夜は敬遠してしまうけれど。著者の思いが勘につくところもあったけれども、総じて面白く読めた。解説があの「さいごの色街 飛田」の井上さんで相変わらずの上から目線なところが私には最後に興ざめでした。2017/09/10
たまご
23
遊郭の仕組みについて,その経営者から娼妓の日常,口入業,モグリ医師,上がりっぱなしの客などなど,多角的に丹念に,10年以上かけての聞きとりをまとめて書かれています.あえて感情的にならぬ,一般人にもわかりやすくなじみやすいその筆致は見事.遊郭はいけない,という道義的な部分だけでは,それが過去,そして形を変えて今も残っているこの社会の問題点を明らかにすることはできない.いけない=見ないふり,知らなくていいことにしてしまう風潮はいかがなものかと感じます.このような仕事が,今後も続いていくことを願うばかりです.2017/03/18
tom
15
どこかの書評で取り上げられていた本。民俗学者の著者は、用事で名古屋に行った。待ち合わせの時間まで余裕があったので、駅裏をウロウロしていた。そうすると、解体工事の現場があった。よくよく見ると遊郭。そして業者が家財道具を処分するため運び出していた。著者は、業者に頼んで家の中に入り、家財道具から生活雑貨、文書などなど目につく物を回収、そこから遊郭研究が始まる。関係者、当事者からの聞き取りがメインだけど、信頼を得るためにゆっくりと時間をかけてのインタビュー。民俗学者の仕事の有り様を見せてもらったという読後感。2017/02/27
みや
14
物語は、名古屋・中村遊廓「成駒屋」の遺構の取壊し現場に偶然遭遇するところから始まる。咄嗟に譲り受けた道具類などから、芋づる式に遊郭の実像を明らかにしていく。宮本常一の薫陶を受けた著者だけに、地道かつ抑制的な検証に基づいているから、浮き彫りにされる真実に凄みを感じる。昭和33年の売防法施行から30年ほど経った昭和末期の取材によるものだが、戦前の娼妓の生き残り、遣り手婆、出入りの業者・医師(もぐり)から直接の証言が得られた意義は大きい。往時の娼妓たちのありように肉薄した名著だ。2024/03/31
イシグロ
14
昭和52年、たまたま名古屋駅裏から歩いてきた著者が、遊郭・成駒屋の解体に遭遇するところから始まります。著者は民俗学の視点から残された民具を読み解き、当時を知る人を訪ねて話を聞いていきます。 民具考察や、関係者からの聞書きはどれも興味深く、展開もスリリング。しかし、そこに映し出される世界はあまりにも辛い。特に、残されていた薬品類への考察や、偽医者のくだりは衝撃的です。(もちろん、ただ残酷であったで終わる本ではないです。) また、あの辺り(近いのです)を通った時に、自分にはどう見えるのかな。まだわからない。2021/02/26
-

- 電子書籍
- 村山さん、宇宙はどこまでわかったんです…