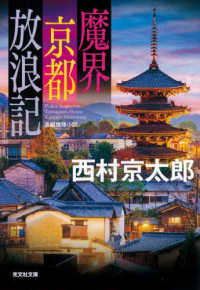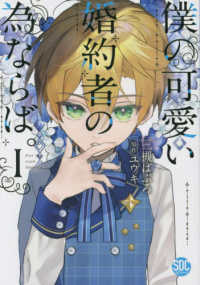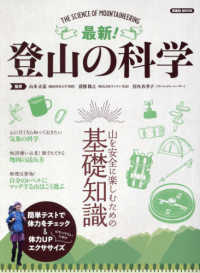出版社内容情報
プロ棋士、作家、観戦記者からウェブ上での書き手まで――「言葉」によって、将棋をより広く、深く、鮮やかに楽しむ可能性を開くための名編を収録。
内容説明
多くの人間をとりこにしてきた奥深いゲーム「将棋」。勝って喜ぶ人、負けて悲しむ人、プロの芸を鑑賞し、楽しむ人。勝敗を争う中に、人の個性と歴史が浮かびあがる。将棋の楽しみは実に盤上に限らない。プロ棋士、作家、観戦記者から、ウェブ上での書き手まで―「言葉」によって、将棋をより広く、深く、鮮やかに楽しむ可能性を開くための名編を厳選収録。文庫オリジナルアンソロジー。
目次
聖性(中平邦彦)
大山名人と棋譜ノート(越智信義)
名人・木村義雄(宮本弓彦)
愛棋家・菊池寛(倉島竹二郎)
知られざるドラマ(真部一男)
棋聖戦の思い出(福本和生)
なっとくなっとく―棋士の引退(湯川博士)
血涙十番勝負―米長邦雄七段戦(山口瞳)
江分利満氏との対局(高橋呉郎)
就位式の敗者(田辺忠幸)〔ほか〕
著者等紹介
後藤元気[ゴトウゲンキ]
1978年千葉県生まれ。観戦記者。フリーライター。指導棋士三段。各棋戦の観戦記やインターネット中継を担当。将棋ペンクラブ大賞・観戦記部門大賞を過去二度受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
R
37
様々な人が将棋について書いた本で、ある種貴重な文化資料的側面もあって面白かった。升田大山といった時代の話、加藤先生の天才っぷりもあるが、桐谷先生が棋士としての頃の話が興味深くてよかった。今の将棋界と異なり、オブラートに包みつつも底意地の悪い辛辣な文章が読めて、これでこそとも思わされるところがとてもよかった。将棋界というものを考える内容もあるし、含蓄の深い文章が選ばれていて、今との違いが色濃く味わえるよい本だった。2024/12/31
kokada_jnet
16
後藤元気の編集によるもの。センスのいい、統一感のあるセレクションだが。将棋と将棋界の「いい面」ばかり強調されてしまった印象が。河口俊彦『対局日誌』の、C2桐谷・本間戦の回と、その描写に対する桐谷七段の反論文が、面白かった。2014/03/21
緋莢
14
先崎学、山崎隆之らプロ棋士、山口瞳、高木彬光ら作家、shogitygoo、将棋観戦などの管理人やブログ等の文章を集めたアンソロジー。<伝説の真剣師小池重明氏と一戦交えさせてもらったのも強烈な体験だった。ケレン味たっぷりの指し回しに初段の僕はジタバタしながら次第に飲み込まれていき圧敗を喫した。>という行方尚史による「追悼 団鬼六」や、「きょうはしんどい。早く投げて帰ります。」という言葉を 何度も聞いたが、早く指して負けるという事はほとんど無かったという村山聖(続く2024/06/15
スプリント
14
収録されているエッセイがバラエティに富んでいて読んでいて飽きがきません。屋敷九段の棋聖戦前夜を綴ったエッセイが面白かったです。最後に編者あとがきで各エッセイの簡単な説明が掲載されているので、読み返す際に重宝します。2015/02/05
そり
12
「愛棋家・菊池寛」一時は、日本は物が豊かになったが心は貧しくなった。なんて言葉を耳にした記憶がある。けれど、昔の棋士は副業でうどん屋やその出前持ちをしないと食っていけなかったっていうんだから、発展して良い国になったのだなあと思う。お金が無ければ是非もなし。▼「十年後の将棋世界」もしも最も悲観的なシナリオになったのなら、将棋ソフトの発展でスポンサーは撤退。興行として将棋は終わる。そしたら発展なんてろくでもない、全くクソよりもつまらない国だぜ、なんて思い直すかもしれない。一ファンは勝手気ままにこんなことを言う2014/02/12