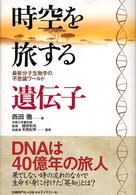出版社内容情報
??通過儀礼?≠ナ映画を分析することで、隠されたメッセージを読み取ることができる。宗教学者が教える、ますます面白くなる映画の見方。
内容説明
映画には見方がある。“通過儀礼”という宗教学の概念で映画を分析することで、隠されたメッセージを読み取ることができる。日本とアメリカの青春映画の比較、宮崎映画の批判、アメリカ映画が繰り返し描く父と息子との関係、黒沢映画と小津映画の新しい見方、寅さんと漱石の意外な共通点を明らかにする。映画は、人生の意味を解釈する枠組みを示してくれる。
目次
予告編
1 『ローマの休日』が教えてくれる映画の見方
2 同じ鉄橋は二度渡れない―『スタンド・バイ・ミー』と『櫻の園』
3 『魔女の宅急便』のジジはなぜことばを失ったままなのか?
4 アメリカ映画は父殺しを描く
5 黒澤映画と小津映画のもう一つの見方
6 寅さんが教えてくれる日本的通過儀礼
7 総集編
著者等紹介
島田裕巳[シマダヒロミ]
1953年東京生まれ。宗教学者・作家。東京大学文学部宗教学科卒業。同大学大学院人文科学研究科博士課程修了。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えりっち
12
あくまで作者の主観であり、読んでいてあまり共感は出来ない本でした。2020/06/08
eriko*
9
通過儀礼というのは、一つの重要な視点ではあるなぁ、と思った。 あまりそれにこだわりすぎると、(ジブリ映画など)本質を見誤ってしまわないかなぁ、とも思いました。 2020/08/19
かやは
8
映画のストーリー展開を「通過儀礼」という宗教儀式を通じて読んでいく一冊。現在は通過儀礼を行うことも個人の自由に委ねられおり、そのため成長出来ずに苦しんでいることもあるかと思う。映画を見ることで通過儀礼を疑似体験し、葛藤が解決することもあるかもしれない。映画は二時間弱という間にいかに演出し、話をまとめるかが重要で、通過儀礼という特別な出来事は、この媒体で表現するのに向いているんだなと感じた。2014/02/28
職商人
8
この様な「映画の見方」もあるのかと感心して読みました。私なども「通過儀礼」をしそこなった人間と思えてきて、それが私の今にいたる未成長の原因かと・・・・・。それにしても、このキーワード、切り口、現代社会を見ているといろいろと思いあたる節があります。2012/10/08
K・J
7
まず、このタイトルのすばらしさよ。単行本は「ローマで王女が知ったこと」だそうで、タイトルの重要さすらも教えてもらった。通過儀礼という民話や神話にも出てくる所に着目して、映画を見ていく。通過儀礼には時間制限があるというところは読まないと気がつかなかった。ローマの休日しかり、スタンド・バイ・ミーしかり。個人的にすばらしいと思ったのは、ジブリ作品、特に魔女の宅急便は、(ジブリ映画版は)通過儀礼をクリアしていないから、キキと最後まで会話が出来なかったのではないかという仮説。腑に落ちる話だった。2015/10/07
-
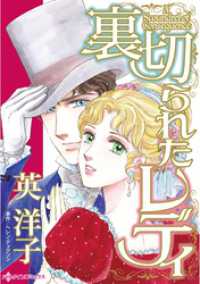
- 電子書籍
- 裏切られたレディ【分冊】 4巻 ハーレ…
-
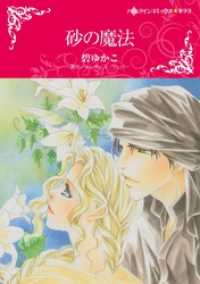
- 電子書籍
- 砂の魔法【分冊】 11巻 ハーレクイン…
-
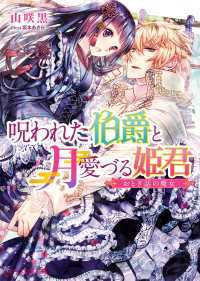
- 電子書籍
- 呪われた伯爵と月愛づる姫君 おとぎ話の…
-

- 電子書籍
- グローバリゼーションとアメリカ・アジア…