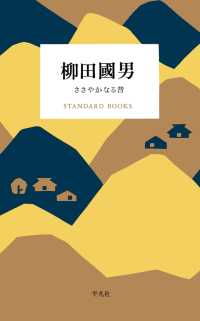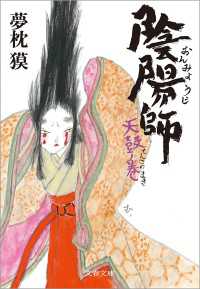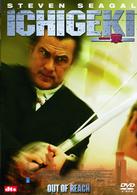内容説明
議論で打ち負かされるのは本当に嫌なもの。自らに非がないにもかかわらず、いつの間にか相手の術中に嵌って二者択一を迫られたり、説明責任を負わされたりして、ディレンマに陥って沈黙せざるを得なかった経験が誰にでもあるはず。相手がしかけた罠を見破り撥ね返すにはどうすればよいのか。社会人として、自分の身を守るために必要なテクニックを伝授する。
目次
第1章 議論を制する「問いの技術」(赤シャツの冷笑―問いの効果;カンニング学生の開き直り―「問い」の打ち破り方 ほか)
第2章 なぜ「問い」は効果的なのか?(村上春樹の啖呵―相手の答えを封じる問い;臼淵大尉の鉄拳―言質を取るための問い ほか)
第3章 相手を操る弁論術(ナポレオンの恫喝―多問の虚偽と不当予断の問い;丸山眞男の対照法―選択肢の詐術 ほか)
第4章 「論証」を極める(プラトンの不安―論争における「根拠」;夏目漱石の摩り替え―論点の摩り替えその2 ほか)
第5章 議論を有利にするテクニック(清水幾太郎の喧嘩―“tu quoque”の技術;丘浅次郎の後出し―発言の順番 ほか)
著者等紹介
香西秀信[コウザイヒデノブ]
1958年香川県生まれ、筑波大学第一学群人文学類卒業。同大学院博士課程教育学研究科単位修了、琉球大学助手を経て、宇都宮大学教育学部教授。専攻は修辞学(レトリック)と国語科教育学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Apple
43
本書を読んで,まず弁論について勉強することの大事さというか,議論において自分を守る知識を身につけることの重要性を認識することができました。一般に用いられることの多い弁論術のトリックと対策をわかりやすく解説しているところが良いと思いました。『主張をした側が立証する責任を負っており,反対する側が課されるものではない』この一点は,弁論における基本として記述されておりましたが私としては結構参考になったところであります。2026/01/08
磁石
25
人間は本質的には論理的な生き物で、理詰めで説得されると精神の敗北を感じてしまう。むしろ情に流されたほうが納得してくれる。そのために使われる詭弁。「問う」こととは、議論を制する技でもある。情報の要求に見せかけて、何事かを論証しようとする意図を含んでいる。沈黙を封じ論証する責任を押し付ける。そんな詭弁を込めた問には、answer=答えるのではなくretort=言い返した方がいい。その「問」の妥当性を問う、アンタにそんなこと言える資格があるのかと。……これぞ、護身術ならぬ護心術2016/04/08
夏野菜
19
何度も読み返し、人におすすめしたい名著。相手に言いくるめられ、うまく言い返せず、なんか違うよなとモヤモヤしてしまう人におすすめ。いわゆる口の達者な奴は知らず知らず自分で身につけているのかもしれないが、そう言った強弁、詭弁には、型がある。それを知っていれば言い返したり無視したりできる。人類が皆、そのパターンを知ってしまえばもはや詭弁は成り立たなくなる。詭弁と言うものを悪用するのではなく、身を守るために知っておくのが大事。詭弁を言われてのほほんとしたお人よしでいると損をする。生きる術として身につけたい。2024/10/12
masabi
18
【概要】レトリックや詭弁を知ることで日常の議論で相手の仕掛けた罠を避けることができる。【感想】小説、対談などの議論を題材にレトリック・詭弁の構造、相手の術中に嵌まらずに切り返す方法を学ぶ。口頭では会話の形式上適切な切り返しを考えるのに時間をかけられないので、まずは相手の手管を見抜けるようになりたい。また、問いかけの特権性と立証責任の考え方は覚えておきたい。使う側としてはレトリック・詭弁を指摘されると不利になる、相手がこちらの思惑外の返答をすると弱くなる。2022/10/25
ヒダン
17
発言者はどのような言葉・表現を選ぶかというところに意図を込めることができる。特に問いという形で発言すると、自分のルールの上で相手の返答を強要できるので弁論術的には強力である。そのような意地悪な問いに対しては、問うこと自体の妥当性を問うような<>を返すことで守ることができる。文学から弁論術的な例を取り上げて説明したり、大学教授の日常としての言い逃れ術も例になっていて固さがとれていて読みやすい。詭弁術を普及させることで詭弁をふるう機会を減らすことができ、詭弁家の優位がなくなっていく。2016/08/05