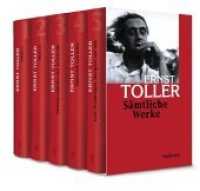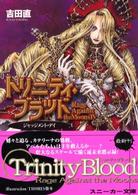出版社内容情報
内容は後日登録
内容説明
四季折々の移ろいのなかで、互いに面識のないふたりの小説家が、文学への深い愛情をこめて、濃密に織りなした往復書簡集。幼少時代の読書体験から古今東西の名作へと、縦横無尽に話題は広がり、繊細な感受性とユーモアを交えた文章で、文学の可能性を語りあう。本を読むことの幸福感に満たされた一冊。
目次
最後の手紙
なぜ恋愛小説が困難に?
言葉、そして文学への恋
幼少の頃の読書の祝祭
天下の剣豪小説『宮本武蔵』
読書の“小魔窟”の中で
『若草物語』と女の子の魂
物語が持つ魔術的一体性
ジェーン・エアの高らかな自由への意志
男女の顔が欠落した風土〔ほか〕
著者等紹介
辻邦生[ツジクニオ]
(1925‐1999)東京生まれ、東京大学卒。1963年『廻廊にて』を刊行し近代文学賞、68年『安土往還記』で芸術選奨新人賞、72年『背教者ユリアヌス』で毎日芸術賞、95年『西行花伝』で谷崎潤一郎賞を受賞。歴史小説を中心に独自の文学世界を構築した
水村美苗[ミズムラミナエ]
東京生まれ。イェール大学卒。1990年『續明暗』を刊行し芸術選奨新人賞、95年に『私小説 from left to right』で野間文芸新人賞を受賞。『本格小説』で読売文学賞を受賞。08年刊行の『日本語が亡びるとき―英語の世紀の中で』で小林秀雄賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
356
辻邦生と水村美苗との間に交わされた往復書簡。古くはソポクレスからおよそ19世紀までの文学、および「書くこと」をめぐってのもの。これらは純然たる書簡なのだが、辻の構成意識によるものか、2人の共作による書簡体小説であるかのような趣きである。プロローグには水村の最後の手紙が置かれる。それはあたかも鷗外の『舞姫』がそうであったごとく、全てが終わった時に回想される物語を紡いでいくかのように。冒頭はこんな風に始まる。「トスカーナの丘の上に建つこの古い僧院はまだ闇の中に沈んでいます」ー実に鮮やかなオープニングである。2022/06/02
ロマンチッカーnao
26
水村さんの日本語亡びるときを読み、感銘を受け本書を読みましたが、この本も最高でした。様々の文学作品を取り上げつつ、文学のすばらしさを文学を愛する少数の僕たちに教えてくれます。僕たちは幸せなんだ。としみじみと感じつつ最後まで読みました。しかし、本書は、辻さんと水村さんの手紙のやり取りだけで進むのですが、手紙を書く、手紙を受け取る。その事がどれだけ幸福なことなのか。内容と共にその事も痛烈に感じました。あ~僕も手紙書きたい。と思いつつ、この悪文を眺め恥ずかしく苦笑いを浮かべてます。2016/07/29
かふ
23
辻邦生は大正生まれで、戦後世代よりは戦中世代なのか?ラテンアメリカ文学ブームを良しとはしなかった。ちょうど青春時代がラテンアメリカブームで、文学観の違いを感じた。水村早苗は世代的には近いと思ったがだいぶ保守的な感じがする。私がサブカル文学オタク過ぎるのかもしれない。水村早苗が読んでいた少女小説(女の子文学と言っていた)は映画やTVで観ていた。辻邦生もエミリー・ブロンテ『嵐が丘』で話が盛り上がるまでは、それほど噛み合っていたとは思わない。水村早苗がフランス文学より英米文学好きなのは英語圏にいたからだという。2023/10/06
風に吹かれて
15
物語の大きな役割のひとつは、物語が読む人を幸福にするということ。登場人物に自分を託したり、あるいは「いやいや、俺は違うぞ」と思いながら登場人物の動きを批評的に追ったり、時空を超えていろいろなことを経験させてくれたり・・・。物語を読む楽しさが伝わってくる往復書簡だった。取り上げられる作品は、多くの人がその名を見聞きしているであろう作品がほとんどで、未読のものを是非読みたいと感じさせるような分かりやすい筆致が二人の読みの深さを思わせる。2017/01/03
ももたろう
13
辻邦生と水村美苗の心温まる手紙のやり取り。彼らの思い出の詰まった本がたくさん出てきて、読者としては素晴らしい読書案内と感じる。ただし、残念なことに、出てくる本の半数以上が未読だったことに加え、彼らの教養の高さについていけないことがしばしばあった。ついていけなくとも、彼らの語る言葉の数々に人間的な温もりや現代を憂う知識人の思想をぼんやりと感じた。また、年月を経て再読したいと思う。2016/01/24


![滝平二郎カレンダー 〈2014〉 [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48729/4872906322.jpg)