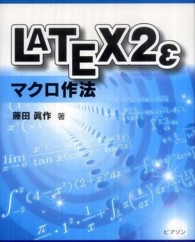目次
団栗
竜舌蘭
糸車
蓄音機
映画時代
銀座アルプス
物売りの声
病院の夜明けの物音
自画像
芝刈
蓑虫と蜘蛛
鳶と油揚
電車の混雑について
日常身辺の物理的諸問題
物理学圏外の物理的現象
自然界の縞模様
西鶴と科学
怪異考
化物の進化
人魂の一つの場合
日本楽器の名称
比較言語学における統計的研究法の可能性について
神話と地球物理学
俳句の精神
連句の独自性
映画と連句
地球を眺めて
天災と国防
著者等紹介
寺田寅彦[テラダトラヒコ]
1878‐1935。東京・麹町の生まれ。父の郷里高知の中学から五高に進学、夏目漱石に英語を学んだ。東大物理学科で実験物理学を専攻、卒業ののちヨーロッパに留学、ついで東大教授。その後、理化学研究所、地震研究所に関係。早くより文筆を好み、漱石の紹介で「ホトトギス」に小品を載せたのを皮切りに、吉村冬彦、薮柑子などのペンネームで数多くの警抜な随筆を書いた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。