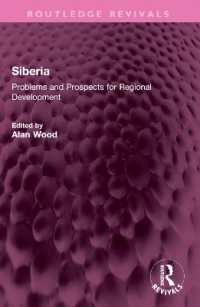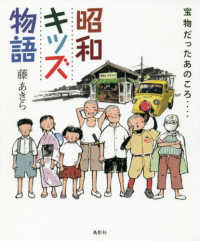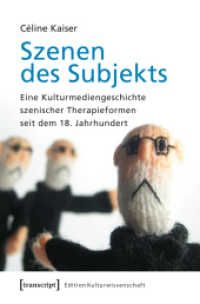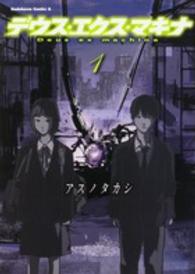内容説明
フルトヴェングラー、ヴァルター、ムラヴィンスキー、カラヤン、アバド…演奏史上に輝く名指揮者28人に光をあて、その音楽の特質と尽きせぬ魅力を描いた名著『世界の指揮者』に、指揮者をめぐるエセーの章「指揮者の風景」、さらにリヒターのバッハ『マタイ受難曲』やクライバーのブラームスなどCDの名盤を語る「指揮者とディスク」の二章を新たに増補しておくる、指揮者論の最高峰。
目次
1 世界の指揮者(ヴァルター;セル;ライナー ほか)
2 指揮者の風景(フルトヴェングラーの思い出;ヴァルターのマーラー;カラヤンの死 ほか)
3 指揮者とディスク(シューリヒト(ブラームス/交響曲第三番)
アンセルメ(ファリャ/『三角帽子』)
ギュンター・ヴァント(ブラームス/交響曲第一番‐三番) ほか)
著者等紹介
吉田秀和[ヨシダヒデカズ]
1913年9月23日、日本橋生れ。東京大学仏文科卒。現在、水戸芸術館館長。戦後、評論活動を始め『主題と変奏』(1953年)で指導的地位を確立。48年、井口基成、斎藤秀雄らと「子供のための音楽教室」を創設し、後の桐朋学園音楽科設立に参加。57年、「二十世紀音楽研究所」を設立。75年『吉田秀和全集』で大佛次郎賞、90年度朝日賞、『マネの肖像』で読売文学賞受賞。2006年、文化勲章受章。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nobi
27
「束の間に過ぎさるものの永遠性」を信じたいのに「たくさんのものが、過ぎさり、姿を消して」、特に演奏評は「とかくやりきれないほど皮相的」と認識した上での指揮者論。それでも、例えばフルトヴェングラーの最後の年の演奏に接することのできた吉田氏は「濃厚な官能性と…高い精神性と、その両方が一つにとけあった魅力」を伝えて、その演奏会場に招いてくれる。スコアを読み解いた上での演奏評はもちろん、各指揮者の生い立ちやナチスとの関係に触れ、時には食事を共にし、先入観を排した演奏・人物評を展開する。どの演奏も聴いてみたくなる。2015/08/09
Tomoichi
13
著者が齋藤秀雄らと「子供たちのための音楽教室」のちの桐朋学園音楽科設立に参加した日本のクラシック音楽の礎を築いた一人であり文化勲章受章者ということ期待して読み始めるが、私には辛かった。1950年代にフルトヴェングラー等の指揮を直に聴いている数少ない日本人の書いた文章なので、貴重な記録として読んでみました。2017/06/07
うた
12
セルのベートーベンが好きで交響曲全集を買ってしまったクチですが、彼はアンサンブルのようにオケを鳴らすというのは、正中を得た表現かと。あとフルベンの章を読んだあと、私には珍しくワーグナーな気分になったので、トリスタンとイゾルデを聴いているところです。全四時間(`・ω・´)。2016/12/29
franz
4
音楽評論は吉田秀和に限る。音楽に対する理解や洞察が深いし、適度に人間に対する考察・描写がある。音楽を書くのも演奏するのも人間である以上、これは自然なことだと、読んで気づく。ただし、特定の人物に心酔して何でもかんでも良いと言ったりすることもない。読んで気持ちのよい評論。 自分の最も好きな指揮者についての言及があったのも個人的に嬉しかった。2024/12/11
訪問者
3
吉田さんが様々な時期に書いた「世界の指揮者」、「指揮者の風景」、「指揮者のディスク」から構成された一冊。吉田さんの文書はいつ読んでも素晴らしい。現代日本で読める日本語文の一つの頂点ではなかろうか。2025/09/30