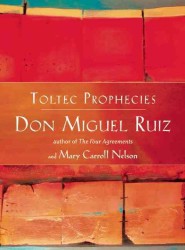内容説明
取扱説明書や役所へ提出する書類を読んで、何がなんだか分からない、という経験はないだろうか?自分の知らないこと、未経験の内容の文章は読むのは難しい、それに比べ、知っていることが書かれている文章は簡単に読める。実は読み方には二種類あるのだ。論文など未知を読むベーター読みと既知を読むアルファー読み。頭脳を刺激し、読書世界を広げるベーター読みを身につける方法とは?リーディングの新しい地平をひらく書。
目次
序章(未知が読めるか;マニュアルがこわい;論語読みの論語)
第1章(わかりやすさの信仰;スポーツ記事;自己中心の「加工」;音読)
第2章(教科書の憂鬱;裏口読者;批評の文章;悪文の効用)
第3章(アリファー読み・ベーター読み;幼児のことば;二つのことば;切り換え;虚構の理解;素読;読書百遍)
第4章(古典と外国語;寺田寅彦;耳で読む;古典化;読みと創造;認知と洞察)
著者等紹介
外山滋比古[トヤマシゲヒコ]
1923年生まれ。東京文理科大学英文科卒業。『英語青年』編集長を経て、東京教育大学、お茶の水女子大学などで教鞭を執る。お茶の水女子大学名誉教授。専攻の英文学に始まり、テクスト、レトリック、エディターシップ、思考、日本語論の分野で、独創的な仕事を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マエダ
112
”本を繰り返し読んだ本のない人は、たとえ、万巻の書を読破していても、真に本を読んだとは言えない””難しい、よくわかったという自信はないが、素晴らしい本である。この手の本を何度も読むのはあたり前である。”納得してしまう理にかなった槍が心に突き刺る箇所が非常に多く、読書関係本の中でおすすめの一冊。2016/12/13
青蓮
95
読み方には二種類あると言う。物語性がない論文など未知を読むベーター読みと文学作品など既知を読むアルファー読み。かつて跋扈していた難解信仰はアメリカから渡来した「わかりやすいことはよいこと」平明至上主義によって淘汰された。その結果、現代は文章に「わかりやすさ」を求めるあまり、未知を読む事をほぼしなくなってしまったと言う(特に学校を終えた大人達が)。難解信仰も平明至上主義もどちらも私は行き過ぎては良くないと思うけれど知を発見し自分の可能性を広げるためには未知を読むのが必要。普段読まないジャンルの本に挑戦したい2019/07/01
おつまみ
61
スポーツなど専門的な知識がないと理解できないことも多い。簡単なようで難しい読書だからこそ、理解しがいがある。2019/11/30
ヴェルナーの日記
53
自分にとって読みやすい本ばかりを読みことは真の意味で「読書」とはいえない。読みにくい本、歯ごたえある本を読んでこそ、読書であるという著者の考え方に新鮮さを感じた。今まで意識することなく読みたい本を選んでいたが、少し見直したほうが良さそうだ、と感じた一書である。2011/03/10
獺祭魚の食客@鯨鯢
48
文章を読むときのあり方として既知を読むか、未知を読むかということがあり、前者をα読み、後者をβ読みと分けられています。 α読みとは、例えばスポーツ新聞で前日のプロ野球の記事を読む際、結果や概要が頭にあるので流し読みでも文章の内容が頭に入ってきます。 β読みはその逆なので読む人間にはハードルが高くなりますが、読了したときに得られる成果は遥かに大きい。 その昔「読んでから見るか、見てから読むか」という映画の惹句がありましたが、α読みにして読む楽しさを台無しにしていますね。 2019/09/26