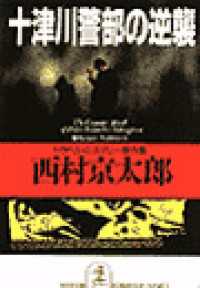内容説明
現代のグローバル化や保護貿易/自由貿易を考えるには、まずその起源を知らねばならない。近年の考古学的発見が明らかにしたように、人類はその黎明期から多種多様な商品を交換してきた。交易は、人間社会が繁栄するための欠かせない土壌であり、ときに諸文明を結びつけ、ときにさまざまな軋轢や凄惨な衝突をも巻き起こす。だが、交易なくして人類はない。知られざるその歴史を、エピソード豊かに圧巻のスケールで描き出した通史。下巻は、オランダ、イギリスなどのヨーロッパ新興国が世界市場に本格的に進出する17世紀から、グローバル化への反発が高まりを見せる21世紀のはじめまで。
目次
第8章 包囲された世界
第9章 会社の誕生
第10章 移植
第11章 自由貿易の勝利と悲劇
第12章 ヘンリー・ベッセマーが精錬したもの
第13章 崩壊
第14章 シアトルの戦い