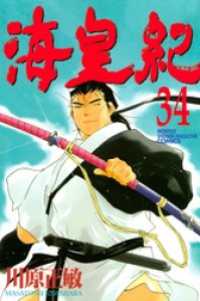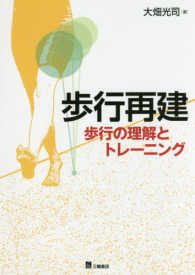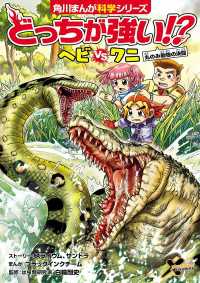内容説明
清朝中国から台湾を割譲させた日本は、植民地・台湾を統治するため新たな統括官庁を組織した。その現地機関が台湾総督府である。初期武官総督時代・大正デモクラシー期の文官総督時代・大戦期の後期武官時代を経て、植民地時代の終焉までの日本支配の全貌を追うとともに、その軍事権・行政権・立法権・司法権の実態を探る。そこで浮き彫りにされるのは、台湾人としての民族意識が自治権獲得に向けた運動と併行して日本統治期に醸成された、という史実だ。台湾独立運動家でもあった著者が、多面的な視点をもって、平明かつ詳細に書ききった名著。
目次
序章 日本と台湾
1 台湾領有
2 初期武官総督時代
3 文官総督時代
4 後期武官総督時代
5 台湾総督府の権力
6 台湾総督府の終焉
著者等紹介
黄昭堂[コウショウドウ]
1932年、台湾・台南市生まれ。別名、有仁。台湾大学経済学系を卒業後、1959年東京大学へ留学(社会科学研究科国際関係論専攻)。国際学修士号につづき社会学博士号を取得。聖心女子大学、東京大学教養学部の講師を経て、1976年‐1998年昭和大学政治学教授。日本留学時から台湾独立運動の主導者として活動し、台湾青年社を東京に設立。その活動のため長らく帰国できずにいたが、1992年、34年ぶりに民主化された台湾へ帰国する。1995年には台湾独立建国聯盟主席に就任し、2000年には台湾総統府国策顧問となる。2011年11月没。昭和大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
さとうしん
nagoyan
スプリント
nnpusnsn1945