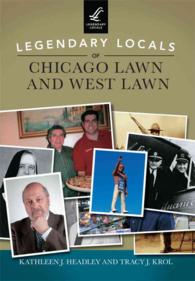出版社内容情報
言語能力はある一時期、ヒトのみに進化した。その仮説がいま、最新科学によって具体的に見えてきた──。知の巨人が言語の本質を語る格好の入門書。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
40
2016年初出。ウォレスは人間の言語についてのどんな主張も従来のダーウィンの適応主義から説明するのは難しいことを初めて指摘(9頁)。ウォレスが「人間の知的、道徳的性質」と呼んだ、生まれてそれほど時間がたっていない不思議な生物学的対象。独創的なイマジネーション、言語と象徴表現全般、自然現象の記録と解釈、複雑な社会的慣習などに対応できる才能で、〝人間的能力〟と呼ばれることもある複合体(76頁)。言語設計の研究で、言語と運動感覚と思考システムの関係についての証拠についての証拠が見つかる可能性がある(108頁)。2018/01/22
ホシ
18
言語学の本かと思ったら…。いや、言語学の本ではあるんですけど”生物”言語学の本でした。言語の誕生について神経科学、脳科学、遺伝学、生物分子学などの観点から論じます。難解。ちんぷんかんぷん。途中から飛ばし読み。ともかく言語の発生や獲得には遺伝子レベルの事象が関わっているという事は理解できました。「私たちだけが、他の動物にはできない、併合という演算ができ、その結果、階層構造をともなう表現を無限に並べることができる」(p.172)この”併合”を司る遺伝子の出現と獲得が言語誕生の鍵なんだろうと思います。2018/05/07
roughfractus02
9
コンピュータ学者バーウィックが主著者だが、言語学という既成の領域にあるチョムスキーの理論を人工知能研究の側から捉え、外的なコミュニケーションに使用される自然言語の習得とは異なる言語概念においてその生得性の斬新さを解釈する。一方、ディープラーニングを行う人工知能には、普遍文法のような思考と解釈はなく、この文法はやはり人間独自であるという点にも触れる。本書は、人間独自の内的思考を遺伝子工学や脳科学を手がかりに探求し、変貌し続けるチョムスキーの理論が、言語の変化ではなく進化の解明をテーマとしてきた点を強調する。2020/05/08
たか
8
名著なんだろうけど難解ですね〜2017/12/21
mim42
7
Berwick et al,「チョムスキー言語学講義」興味深く読んだ。言語を生み出す仕組みの進化に関する、比較的最新の話題。大人の事情で「チョムスキー」全面推しな売り方だが割り切ろう。問題は訳質。おそらくアルゴリズムについての理解が無さそうな訳者による逐語訳。Google翻訳にも可能。後書きも無し。ピケティ和訳と同じ状況。原書読めよ→おっしゃる通り。しかし、これほど知的好奇心をそそられる本をしばらく読んでいなかった。2017/11/28