出版社内容情報
魔女狩りの嵐が吹き荒れた中世、美徳と超自然的力により崇められる聖女も同時に急増する。両極の女性像が噴出した西洋中世とは何なのか? 謎に迫る。
内容説明
中世末から近世にかけて、西洋世界において魔女狩りの嵐が吹き荒れる。しかし、それと時をほぼ同じくして、その美徳と超自然的力によって聖女と崇められる女性たちも現われる。幻視を経験し、恍惚に浸り、空を飛ぶといった、人間を超える特徴を共有する魔女と聖女は、あらゆる点で表裏の関係にあった。なぜ同時期に、女性に対する嫌悪と礼賛とがこれほどまでに高まっていったのか?そこには時代のどんな精神性が働いていたのか?魔女狩りが行なわれなくなった後も残りつづけた女性の魔性に対する畏怖と信仰をめぐる論考を増補。
目次
第1章 魔女(魔女狩り;魔女集会「サバト」 ほか)
第2章 聖女(閉ざされし聖女のその;男装する聖女 ほか)
第3章 魔女と聖女の狭間で(モデルとしてのイヴとマリア;女のからだ ほか)
第4章 したたかな女たち(教会法と世俗の法;女性の仕事 ほか)
第5章 女性の文化は存在したか(糸巻き棒の福音書;読書する女 ほか)
補章 近現代の魔女と聖女―宿命の女をめぐって
著者等紹介
池上俊一[イケガミシュンイチ]
1956年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は西洋中世・ルネサンス史。独自の切り口から西洋社会の深層に迫る研究で知られる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TSUBASA
20
中世ヨーロッパで協会の標的となり陰惨な処刑の対象となった魔女と、聖なる行いにより奉り上げられた聖女。相反する二つの女性像がなぜ中世ヨーロッパでは盛んに持ち上げられたのか。魔女は別の本である程度その成り立ちを知っていたのだけど、聖女とは何かに興味を引かれて読んだ。後半はヨーロッパの女性史だったので若干期待と違っていたけど。こうして対比してみると、語感とは違って罪もなく吊るし上げられた魔女よりも宗教を信じきって奇跡まがいの経験を声高に叫ぶ聖女の方が薄気味悪い存在に見える。2015/09/03
爺
11
聖女と魔女というキリスト教文化圏での中世初期から近代までの女性の立場を掘り下げた傑書。キリスト教圏においてどれだけ女性性が虐げられ服従を強いられてきたのかが、オカルトではなく史実として理解できる。そして読み終えると、現代の欧米主導の男女平等概念に含まれる宗教的バイアスの反動に関しても理解できる。フェミニストとかそういうことではなく、この人的資源が枯渇した現代で、性別に拘るような人は自分の価値観の源泉がどこにあるのかを確認するためにも読んで欲しい本。トランプとか安倍みたいな復古主義者には響かないだろうけど。2019/12/07
スターライト
8
魔女も聖女も男から見た女性の一面。その人が女性をどう見ているかを表現しただけのことのような気もするが、女性は本書をどう読んだのか。それはさておき、中近世のヨーロッパはやはりキリスト教を抜きにしては語れない。それが色濃く表れた女性史。読みながら、他の地域、たとえば日本や中国などは女性をどうとらえたかが気になっていた。もちろんヨーロッパの例にもれず、日本でも女性は弱い立場であり、男性優位の時代が長く、それは今でも変わらない。アジアにおける女性観の変遷も読んでみたい。2018/10/27
getsuki
8
本屋にて衝動買い。魔女と聖女とは紙一重であり、女性は魔女とも聖女ともなり得る。その判断基準が宗教的なものであったり道義的なものであったり、時代背景的なものであったりという違いはあれど、男性の視点からというのは現代に至るまで変わることはない。むしろこうまで手前勝手に言いたい放題、読み方によってはただの被害妄想じゃないの?という発言が真面目に学問として成立していた事に驚きを感じる。2015/07/03
けいしゅう
5
魔女と聖女。両者はともにキリスト教により、聖書を根拠とするミソジニーを原動力として「発明」された。本書はその男性原理に貫かれた極端な女性観の「犠牲者」たちを幾例もの資料を挙げて解説する。 しかし、受動的に所与の運命を受け入れるのではなく、女性の特性や尊厳を声高に主張し、これを守ろうと奮闘した女傑もいた。十四、五世紀に生きたクリスティーヌ・ド・ピザンだ。彼女の女性賛美はやがて女性による女性の積極的評価を生み出した。表紙の胸を開けた修道女は今まで抑圧してきた女性性を、その女性観に則り開放した姿を象徴的に示す。2018/01/22
-
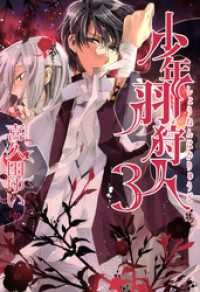
- 電子書籍
- 少年羽狩人: 3 ZERO-SUMコミ…








