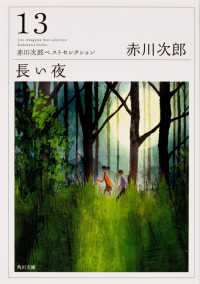出版社内容情報
近代国家の枠組みに縛られた歴史観をくつがえし、列島に生きた人々の真の姿を描き出した、歴史学・民俗学・人類学のコラボレーション。解説 新谷尚紀
内容説明
近代国家の枠組みで考える歴史観を根底からくつがえし、列島に生きる人々の真の歴史を構築しようとした4人の歴史学者・民俗学者によるスリリングな討論。東アジア海域の地理や交流史を検討することで「日本」を構成する人々の多様性を描き出し、さらに、「日本」の中における地域ごとの伝承の違い、祀りの際の男女の役割の違い、ハレの日の食事の違い等を精査し、差別観の変遷を追うことで、この小さな列島に、出自の違う複数の文化があることを明らかにしていく。文献史料と民俗資料を融合させ、立体的な日本像を構築してみせた新しい歴史記述の嚆矢。
目次
1 歴史学と民俗学―その歴史と現在
2 地域史の視点―これまでの地域史・これからの地域史
3 国境をはずして考える日本史
4 異人―文化の内と外
5 男と女
6 老人と子供
7 衣食住と差別
著者等紹介
網野善彦[アミノヨシヒコ]
1928‐2004年。専攻は日本中世史
塚本学[ツカモトマナブ]
1927‐2013年。専攻は日本近世史
坪井洋文[ツボイヒロフミ]
1929‐88年。専攻は民俗学
宮田登[ミヤタノボル]
1936‐2000年。専攻は民俗学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
40
1989年初出。史学と民俗学を、文書対民間伝承という対立関係にしてしまう点に問題があった(024頁)。網野氏:古島敏雄さんの『子供たちの大正時代』は個人史(080頁)。宮田氏は男女の陰部をそのまま発言されている(228頁)ので、御想像にお任せします。坪井氏:男性論理で否定される教理を、日本仏教は女性に押しつけている(235頁)。誰かが犠牲になるシステムは変える必要がある。京大の阪本寧男さんは、農学者や農林省方針は、一貫して里における農業の近代化、合理化を目指した。2016/05/03
うえ
5
「マレビト観というのは、祭りの日が来たから神が来る…もてなしたんだから、終ったら、どうぞ早くお帰りください…ところが、沖縄本島から宮古、八重山のほうへいくと、神が来るから祭りをする」「興味深いのは男のお籠りは性的要素を一切含んでいない。むしろ、そういう部分を不浄部分として、なるべく、排除しようとしていた。ところが、女の祭りになると、性的要素を打ち出すことによって、女の家ないし女の天下を主張しようとする。この違いが江戸時代の農村社会の中に普遍化した要素として存在している」2016/08/26
しびぞう
2
面白かった!「温故知新」とはよく言ったもので、過去を振り返ることが先の解決策を知る最短距離であることが認識できた。本書のベースになっているのが1983年に行われた対談だというのがまた興味深い。歴史を巡る話もいつか虎のバターのように何かを産むのか溶けてしまうのか、どちらなのだろう。2018/02/13
のりべぇ
2
結構、時間がかかったが、面白かった。時代よって学問の流れがこんなにも変化してることを再認識できたかも。 マルクスって影響力大きかったのね。 今の国境に問われることなく、歴史を見るほうが楽しいような気がするなぁ〜2015/08/16
T.M.
2
解説にもあるように1章の「歴史学と民俗学」の部分は学史と問題点が整理されていてわかりやすい。2章から7章の個別のテーマに関しては、4人がもうお互いが何を主張しようとしているのかほとんど知っているのか、または議論が紛糾したところはカットされているのか、不思議なほどに平和。討論で結論を出すというよりは、問題意識の共有という面が大きい。何かを教えてもらう本というより、何かを考えるきっかけとなるような本だろう。個人的には地域史と個人史の議論が楽しめた。2015/06/07