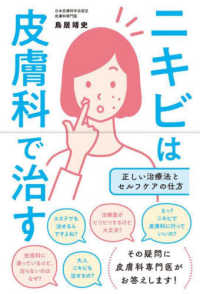出版社内容情報
近代を根本から問う日本独自の哲学が一九三〇年代に生まれた。西田幾多郎・田辺元・和辻哲郎・九鬼周造・三木清による無の思想の意義を平明に説く。
内容説明
模範としてきた西洋近代の諸理念に根本的な危機が訪れた1930年代、この国でも初めて独自の哲学が生み出されていく。それは、「イデア」「神」「理性」といった形而上学的原理によって世界を根拠づける試みを徹底的に批判する、「無」の哲学であった。西田幾多郎・田辺元・和辻哲郎・九鬼周造・三木清ら、「京都学派」の哲学の全体像をわかりやすく説く、入門書の決定版。
著者等紹介
田中久文[タナカキュウブン]
1952年生まれ。東京大学文学部倫理学科卒業。同大学院博士課程修了。日本大学教授をへて、現在、日本女子大学人間社会学部教授。文学博士。専門は倫理学・日本思想史・日本文化論。日本の近代哲学を伝統思想との関連のなかで読み解き、現代の倫理学的課題に生かそうと試みている。主な著書に『九鬼周造―偶然と自然』(ぺりかん社、第一回中村元賞受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
25
無の哲学が日本で形成されていったのは、昭和に入って、1930年代になってから(016頁)。西田幾多郎:物の心の存在は疑おうと思えばいくらでも疑うことのできるものだ(027頁)。純粋経験は原初の経験。原始的な事実、唯一の実在。創造的発展が自己の根源への還帰、自己の根源への帰還が創造的発展(035頁)。知的自己は自身を意識する、自覚するもの(051頁)。創造的世界の創造的要素=個々の主体(064頁)。絶対矛盾的自己同一=絶対無のあり方(066頁)。逆対応=絶対者に対することで真の自己が自覚(068頁)。2015/06/13
mittsko
7
強くおすすめ! ※ 授業のテクストとして皆で読んだ。とにかくよく勉強させていただきました。専門家ではないので確定的なことは言えないが、本書は、いわゆる京都学派の哲学についての理解として、偉大な達成のひとつであることに間違いはございませんでしょう。なにしろ読みやすい、解しやすい(哲学の初学者である学生さんたちにはかなり難しかったようだが)。それは、個別の理解と、「「無」の思想」として「日本の哲学をよむ」という定見とが、ぴたりと嚙み合っていることの表われでしょう。これぞ教科書、という偉大なお仕事です。2021/04/29
ポン・ザ・フラグメント
6
西田・田辺・九鬼・和辻・三木らいわゆる京都学派の哲学を、「無」を固定軸として簡潔かつわかりやすく解説している。とくに「無」に豊饒さを見た西田と、人間の「虚無」しか見出せなかった三木を両極に置いて、他の三人をその間に位置づけるパースは納得しやすい。しかし、懺悔道なんて言った後も、個は種のために滅尽しなければならないとする田辺はやっぱり心情的に受け入れがたい。様々な桎梏から逃れようとして逃げきれなかった九鬼の思想の方が好もしい。三木のお人好しぶりというか行き当たりばったりの生き方も悪くはない。2018/04/04
Ex libris 毒餃子
6
日本の哲学、特に京都学派について書かれた本。無、というキーワードを介して5人の哲学者を紹介している。2015/10/18
politics
4
西田から始まり、田辺、和辻、九鬼、三木の五人の哲学者を「無」のキーワードで主要著作を読み解いていく構成の一冊。西田と田辺は特に独特の用語が飛び出してくるため難解だったがそれでも分かりやすく書かれている方だろう。田辺や和辻の主張がしばしばナショナリズム的だとの批判を耳にするが、本書を読んだ限りではそこまで言われる程なのかと思わされた。次は原点に進みたいと思う。京都学派の哲学を知る入門書としては丁度良いのではなかろうか。2020/08/02