内容説明
寛延年間に生まれた居酒屋は、雨後の筍のように増え続け、文化文政の頃には人口比率でほぼ現在と同じ規模の産業に成長する。食文化を豊かにし、さらには幕府の各種規制を撤廃させていく原動力ともなった居酒屋の歴史を、日記や川柳、随筆、書簡、触れ書などから丹念に掘り起こす。
目次
江戸の居酒屋の繁盛
酒屋ではじまった居酒
居酒屋の誕生
煮売茶屋と居酒屋
江戸で飲まれていた酒
酒造規制と規制の緩和
関東の地廻り酒
酔っ払い天国・江戸
居酒屋と縄暖簾
多様化した居酒屋
鍋物屋の出現
居酒屋の営業時間
居酒屋の客
居酒屋で飲む酒
居酒屋の酒飲み風景
居酒屋のメニュー
苦難を乗り越えてきた居酒屋
著者等紹介
飯野亮一[イイノリョウイチ]
早稲田大学第二文学部英文学専攻卒業。明治大学文学部史学地理学科卒業。食文化史研究家。服部栄養専門学校理事・講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
36
将軍家重のときに居酒屋誕生(039頁)。煮売茶屋:煮物を中心に簡単な食事と湯茶、酒などを出した茶屋。煮売屋、煮売見世ともいう(044頁)。史料、図版多数で臨場感もある。大量に米を消費する酒造りは米価に影響。酒造量が絶えず制御されていた。江戸時代には、だれでも勝手に酒造りをすることができなかった(084頁)。縄暖簾:居酒屋のトレードマークに(119頁)。居酒屋は2013年の口述試験のカードに出たが、私は選ばなかった。2015/06/08
いちろく
23
紹介していただいた本。居酒屋が好きな人にピッタリの1冊。単なる薀蓄本ではなく、シッカリとした資料や文献に基づく考察が凄い。居酒屋の誕生から始まる歴史だけではなく、日本酒やアテの歴史も書かれており、居酒屋が好きな人に、そっと話したくなる内容の数々。特に、西高東低の使われ方に妙に納得してしまった。気圧配置のコトバですが、江戸時代のお酒が西日本から東日本へと流れる事として作中で使用されており上手いな、と思いました。江戸時代と今のマグロの価値観の違いも、食文化の違いがハッキリと認識出来る点で面白い内容でした。2015/07/25
tama
21
他市図書館からお取寄せ 吞む食う好き~ いやー面白かった!知らないこと一杯。芭蕉の「ふくとしる」は河豚魚汁で、「河豚&汁」じゃないのね!銚子と徳利は違うのか!ジョン万次郎が帰ってきた頃、居酒屋にお一人様で徳利傾ける女性が!犬公方のちょっと前の頃、鮟鱇の吊るし切りやってる料理屋の調理場は板敷で料理人は裸足、その板の床にじかに魚置いて場捌いてる~。江戸は酒飲みが日本一の数、関西から船便で届く酒はいい具合にエージングされ関西で飲むより美味くなっていた。燗は人肌が最高とは書いてないが、燗と言ったら熱燗と思うなよ!2017/06/24
gollum
17
江戸は「呑みだおれ」なのだそうだ。食文化史のとても面白い本。以前、日本在住の外国の方々が日本を語る企画のTV番組で、日本の居酒屋を絶賛していた(旨いものが少しずつたくさん食べられる、よいサービス等)が、その源流は江戸時代にあったわけだ。巻末12頁に及ぶ膨大な参考文献リストから引用した狂歌・川柳・お触書も興味深いがなんといってもたくさんの居酒屋風景の図版がとても楽しい。今も昔も変わらないなあ。ルイス・フロイスが指摘しているが、どうも昔から日本の酔っ払いのマナーは最低だったようなのが恥ずかしいが。2014/08/23
本木英朗
15
日本の現代食文化研究家のひとりである、飯野両一による、研究書のひとつである。古くより日本酒は伊丹や池田、富田など関西の町が名産地であった。しかし酒を主役にたのしむ居酒屋は、京や大坂ではなく、産地から遠く離れた江戸で生まれた――という話から始まる。久々の料理研究本で会ったけども、本当に様々なことが書かれてあって、本当に超凄かったです、ハイ! また折を見て読もうと思う。2024/09/06
-
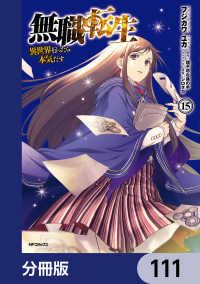
- 電子書籍
- 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~【…
-
![月刊少年マガジン 2018年10月号 [2018年9月6日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0580871.jpg)
- 電子書籍
- 月刊少年マガジン 2018年10月号 …
-

- 電子書籍
- ストライク・ザ・ブラッド16 陽炎の聖…
-
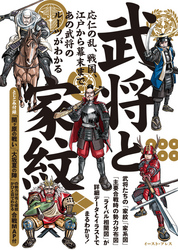
- 電子書籍
- 武将と家紋 - 応仁の乱、戦国、江戸か…





