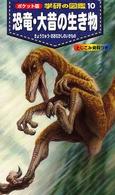出版社内容情報
軟禁状態の中、数人の手勢でなぜ源頼朝は挙兵に成功したのか。鎌倉幕府成立論に、史料の徹底的な読解から、新たな視座を提示する。
内容説明
わずかな手勢で挙兵し、征夷大将軍にまで上り詰めた源頼朝。しかし時を同じくして立ち上がった木曾義仲や、頼朝に反旗を翻した弟義経は、京に入りながらも天下を手にすることはなかった。頼朝にあって彼らになかったものは何か。それは地理的要因にもまして重要な、挙兵の正統性を認めさせる力だった。頼朝は後白河法皇を武力で護りつつ、武家はつねに天皇のためにあるという姿勢を貫くことで、朝廷の信頼を得ていく。それを見て各地の武家勢力も、頼朝に従う道を選んでいった。史料の徹底的な読み込みにより、頼朝と内乱の時代をリアルに描いた、鎌倉幕府成立論の名著。
目次
中世はじまる(頼朝勢力の誕生;平家クーデター ほか)
京攻めの条件(諸勢力の分立;頼朝の対朝廷工作 ほか)
東から西へ(一時的持久戦;一一八四年初頭の交渉 ほか)
守護・地頭・兵粮米問題(対朝廷交渉の開始;守護について ほか)
朝廷と幕府(義経事件の責任問題;貴族社会と頼朝 ほか)
著者等紹介
河内祥輔[コウチショウスケ]
1943年北海道生まれ。東京大学文学部国史学科卒、同大学大学院博士課程単位取得満期退学。北海道大学文学部教授、法政大学文学研究科教授を経て、現在北海道大学名誉教授。専門は古代から中世にいたる政治史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
中年サラリーマン
6
頼朝のリアリズムがなかなか面白かった。まだ自勢力が弱いときは奥州藤原氏を味方につけるために義経を重要な場面で使って北の守りを固め、天皇家の後継争いを利用して関東勢力をまとめ、かと思えば世間の追い風を得るために天皇と交渉し信頼を得、天皇の信用を盾に平家を追い落とす。さらに西国を手中にできたと分かると義経のみ西国に残した上で冷遇し、謀反を起こさせるきっかけを作り奥州藤原氏に攻め込む大義名分をえる。こう見るとなかなかの人物ですな頼朝は。失敗したのは後継者育成ぐらいか。2013/08/15
浅香山三郎
3
本文に付随する注の量が凄いが、いちいち丁寧に読まなかつた。全体の筋としては違和感がないのだけれども、わざわざ補注を長く書くのなら、改稿して文庫化した方が有り難かつた。2017/10/03
ma3
1
「1180年代内乱」を軸にしてこの時期展開した歴史を紐解きながら、なぜ頼朝が幕府を開くに至ったのかを明示した書です。幕府が成立した時からを「中世」と位置づけたことや、「幕府は後白河に直属する」などといった独特の歴史認識を提示しており、刺激に満ちた内容です。しかも、それを導き出したのにごく一般的な史料を使っている点が説得性を高めます。著者曰く、内乱を経ることでその地位と権威を上昇させたとする「後白河」。やはり、この時代のキーパーソンは「後白河」なんだと再認識。ここをもっと深めた探究をしたいものだ。2013/09/22
-
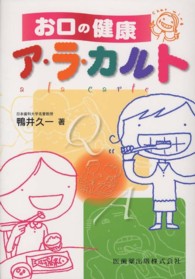
- 和書
- お口の健康ア・ラ・カルト