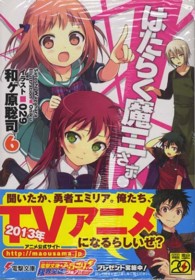出版社内容情報
美しく心地よい住まいや、調和のとれた街並みを、近代的な工法を用いて作り出そうと試みた、バウハウス初代校長最晩年の講演録。
内容説明
モダンデザインを語る上で欠かすことのできないバウハウス運動。その先頭に立ったのが建築家ヴァルター・グロピウスである。空間の使いやすさ、心地よさ、そして美しさを同時に実現させるにはどうしたらよいのか?街にはどぎついネオンや標識が溢れ、新旧の建築物が無秩序に並ぶ。一歩建物に入れば使い勝手を無視したデザインの数々が…。1954年に世界一周のフィールドワークを行ったグロピウスは、自分たちの伝統的な美意識を共有することの重要性を説き、近代的な工法によっても意識しだいで調和のとれた美しい建築・街づくりが可能であると訴える。20世紀デザイン論の名著。
目次
デモクラシーのアポロン
内奥の羅針盤
多様のなかの統一
生命の樹とセールスの悪循環
近代社会における建築家の役割
生活との新しい協定
建築における伝統と連続性
日本の建築
美術館の設計
劇場のデザイン〔ほか〕
著者等紹介
グロピウス,ヴァルター[グロピウス,ヴァルター] [Gropius,Walter]
1883年‐1969年。モダニズムを代表するドイツ出身の建築家。ル・コルビュジエ、フランク・ロイド・ライト、ミース・ファン・デル・ローエと共に近代建築の四大巨匠に数えられる。現代工芸、建築に影響を及ぼしたデザイン学校「バウハウス」の創立者・初代校長。主な設計に旧パンナムビル、ファグス靴工場がある
桐敷真次郎[キリシキシンジロウ]
1926年生まれ。首都大学東京名誉教授。工学博士。専門は西洋建築史。建築や建築史に関わる著書・訳書が多数ある。2012年度日本建築学会賞大賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
ラウリスタ~
2n2n