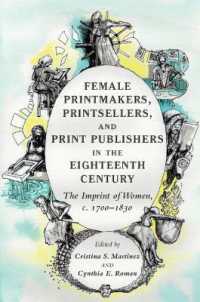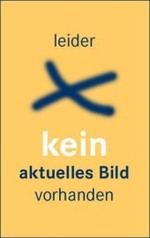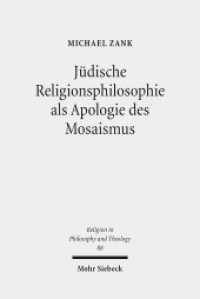出版社内容情報
第2巻は、人間の認識(六処)の分析と、ブッダ最初の説法の記録である実践に関する経典群、祇園精舎を訪れた人々との問答などを収録。解説 佐々木閑
内容説明
ブッダはなにを語り、どのように説いたのか。その教えを最も純粋なかたちで伝える最古層の重要な仏教経典の集成。阿含=アーガマとは伝承されてきた聖典を意味する。これらの経典群のなかには、あらゆる宗派を超えた仏教の原初のすがたがあり、その根本がある。本書は厖大な阿含経典群のなかから、よく古形を保ち、原初的な経と判定される諸経をとりあげ、パーリ語原典からの現代語訳と注解で構成。第2巻は、ブッダの認識論「人間の感官(六処)に関する経典群」と、最初の説法の記録「実践の方法(道)に関する経典群」、それに祇園精舎を訪れた人々との問答とエピソードを収録。
目次
人間の感官(六処)に関する経典群(六処相応;受相応;閻浮車相応 ほか)
実践の方法(道)に関する経典群(道相応;覚支相応;念処相応 ほか)
詩(偈)のある経典群(諸天相応;天子相応;拘薩羅相応 ほか)
著者等紹介
増谷文雄[マスタニフミオ]
1902‐87年。北九州市小倉生まれ。東京帝国大学文学部宗教学科卒業。東京大学、東京教育大学、立教大学、東京外国語大学、大正大学などで教鞭をとり、都留文科大学学長を務める。ハーバード、シカゴなどの大学でも講義(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
16
この巻では眼・鼻・耳・舌・身・意を説いた経典、四諦八正道等仏教の根本を明らかにした経典、そして経中の登場人物が様々な詩を説いている経典が集録されている。成道直後の仏陀に訪れた魔や梵天勧請、そして初転法輪といった仏教にとって一番重要と思われる箇所もこの巻にある。特に初転法輪で四諦八正道が説かれ、仏教が成立していく部分は身が震えるほどの感動。原始仏教の経典は読んでいると心が鎮められるので、余裕がなくなった時や不安感に襲われた時に読むようにしている。これもそのような時に何度となく読み返したい一冊になった。2012/10/01
記憶喪失した男
9
新しくうるところはなかった。一か所、釈尊が不死を説いているところがあった。 2017/07/12
恥づい「自宅警備員」
1
そもそもヴィパッサナー瞑想は経典でどう語られているのかっていうのが知りたくて買ってみた。なんか暗唱したくなった。2015/05/19
デキストリン (皐月はじめ)
0
感想・連想 古代のアファメーション。2500年前に考えられたのかと思うととても驚く。2014/10/09
やまえつ
0
阿含経典のうち人間の感官に関する経典群と実践の方法に関する経典群と詩のある経典群からなる。実践方法を説いた経は具体的な実践方法が分かり勉強になる。詩のある経典群では、コーサラ国のパセーナディー王とのエピソードが印象に残った。2012/10/25