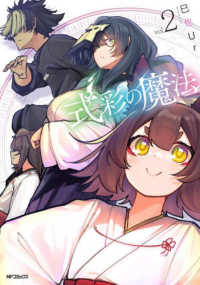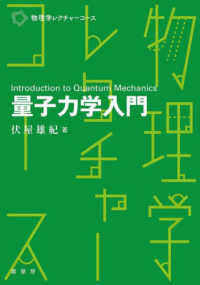出版社内容情報
いにしえから庶民が辿ってきた幹線道路・東海道。日本人の歴史を、著者が自分の足で辿りなおした名著。東篇は日本橋より浜松まで。
内容説明
いにしえの昔から、日本の幹線道路として生きてきた道、東海道。庶民が辿った東海道五十三次は、江戸時代、いったいどのようになっていたのか。試みに二万五千分の一地図を持って歩いてみれば、国道や高速道路の裏側に、昔の旅人が憩ったであろう一里塚や飯屋が、神社やお寺、並木までもが、いまなおひっそり残っているのが分かる。私たち日本人の歴史が刻みこまれた街道を、著者が実際に自分の足で辿りなおした名著。上巻は日本の起点だったお江戸・日本橋を出発して、浜松・本坂越まで。全行程の地図を完備。
目次
東海道の旅
東海道五十三次(日本橋より品川へ;品川より川崎へ;川崎より神奈川へ;神奈川より程ヶ谷へ;程ヶ谷より戸塚へ;戸塚より藤沢へ;藤沢より平塚へ;大山道;平塚より大磯へ;大磯より小田原へ ほか)
著者等紹介
今井金吾[イマイキンゴ]
1920年東京神田生まれ。早稲田大学卒業。日本経済新聞社入社、札幌支社長などを経て、江戸・街道の研究に専念。2010年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
21
1974年初出。 浅井了意『東海道名所記』、 貝原益軒『吾嬬路之記』、 太田南畝『改元紀行』、 滝沢馬琴『羇旅漫録』は 重要文献のようだ(025頁)。 地名や名所はゴシ太。 生麦事件碑(056頁)。 1862年、島津久光の行列前を 横切った英国人リチャードソンらを 薩摩反しが殺傷した事件。 地福時には島崎藤村の墓(090頁)。 天竜川越え。 運賃について[名所記]は 「小天竜、大天竜、舟渡しの川なり。 武士には船賃なし。商人、 百姓には銭6文をとる」(238頁)。 2014/06/05
tama
7
図書館本 読むきっかけは確か古今亭志ん生が無一文で東海道を名古屋から東京へ帰るときのはお話だったと思う。なかなか古い本で私が就職した年の出版。だが図書館にあったのは京都到着まで含まれ、前半だけ読むことに。静岡~岡崎辺りのこと、細かく言うと金谷ー見付ー浜松ー舞阪辺りが知りたかったから。新居~弁天が船便!北の陸路に比べりゃ早いことは間違いないけど。お上は何が何でも新居関所でチェックしたかった?見付西坂の姫街道(旅人往来ご禁制!)入口で東海道を南下させ代官所前を通らせるのも同じ理由だな。地図はまあまあ見易い。2018/07/12
氷柱
6
499作目。6月22日から。知っているようでほとんど知らない東海道を辿る本の前編。序盤は関東住まいということもあって比較的馴染みがあったが後半はちんぷんかんぷん。知らない土地は多い。それぞれの場所にそれぞれの風土が宿っていて、過去の日本はまるで海外のようだとも感じられた。もしかすると今でもそのような風潮が残っているのかもしれない。一歩外に出れば異なる文化があり、人々の生活様式にも多様性があることがわかる。後編の西篇も楽しみだ。2019/06/24
tokomadarate
0
東海道五十三次歩いてみたくなりました。それにしても各宿場に飯盛女なる職業女性がいたとは新発見。2016/01/14