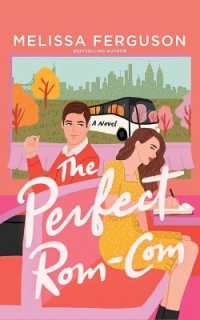内容説明
日本が生んだ世界で一番有名な仏教者・鈴木大拙。禅に関する書物を数多く英語で出版し、たびたび海外に招かれ講演を行った大拙の仏教は、日本の仏教徒のみならず、ユングやハイデガーといった西洋の思想家をはじめ、ビート・ジェネレーションと呼ばれる人々をも魅了した。本書では、今では読むことが難しい、雑誌への投稿論文や、西田幾多郎ら近しい人たちへ宛てた書簡を、編年体で収録。すべてを知ることのできる仏の智慧=「般若」と、すべての生きとし生けるものを救う仏の慈悲心=「大悲」が融合する大拙特有の「禅」がどのように作り上げられていったのか、その思想の道すじが分かる、学芸文庫オリジナル編集。
目次
在米時代(一八九七~一九〇八年)(旅のつれづれ(抄)
一八九八年三月三十日 西田幾多郎宛書簡 ほか)
帰国後(一九〇九~一九二〇年)(緑陰漫語(抄)
一九一一年二月二十三日 ポール・ケーラス宛書簡 ほか)
京都時代(一九二一~一九三〇年)(政治より宗教へ;起て若い君等よ ほか)
十五年戦争期(一九三一~一九四五年)(日本精神と禅の側面観;一九三六年二月二十七日 山本良吉宛書簡 ほか)
敗戦後(一九四五~一九六六年)(一九四五年八月十六日 加納実宛書簡;一九四五年八月二十二日 務台理作宛書簡 ほか)
著者等紹介
鈴木大拙[スズキダイセツ]
1870‐1966年。世界中の人々に影響を与えた仏教者。「大拙」は円覚寺に参禅し、師・釈宗演より授けられた居士号で、本名は貞太郎。1897年に渡米し、出版社にて禅思想の英訳本を刊行。1909年の帰国後も、大乗仏教を広く世界に発信した
守屋友江[モリヤトモエ]
1968年生。阪南大学教授。明治学院大学大学院国際学研究科博士後期課程修了。専門は宗教思想史。スタンフォード大学文化社会人類学部客員研究員、デューク大学神学部客員教授等を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
karutaroton
マウンテンゴリラ
マウンテンゴリラ
1.3manen