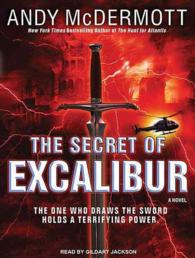内容説明
日本とはどんな国なのか、なぜ米が日本の歴史を解く鍵なのか、通史を書く意味は何なのか。きわめて枢要でありながらも、これまであまり語られてこなかった興味深い問題の数々。先鋭的な現代日本史学の泰斗、網野善彦、石井進が、古代律令制から明治時代に至るまでを、エキサイティングに、そして縦横無尽に語りつくす。対談形式のため、高度な内容であるにもかかわらず、読者にも理解しやすく、読み進むにつれ、この日本という国の真の姿が眼前に立ち現われてくる。今までイメージされてきた国家像や、定説とされていた歴史観に根本的な転回を迫る衝撃的な書。
目次
第1章 通史を書く意味
第2章 なぜ「米」なのか
第3章 支配者はなぜ「米」に固執するのか
第4章 天皇と「米」
第5章 「百姓=農民」は虚像か
第6章 倭国から日本へ―国号の問題
第7章 農本主義と重商主義
第8章 差別・被差別はどこからくるか
第9章 歴史のつくる虚像―まとめ
著者等紹介
網野善彦[アミノヨシヒコ]
1928‐2004年。東京大学文学部国史学科卒業。日本中世史専攻
石井進[イシイススム]
1931‐2001年。東京大学文学部国史学科卒業。日本中世史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
26
網野氏の著作読む度に刺激的なのは自分の歴史観の問い直しを迫ってくる提起があるから。/学問だけではなく、これまでの人間観の現れだと思うのです。まず人間は自分のための食べるものを生産して、満腹して、余った物、余剰生産物を市場に持っていって商品として売るというのが、自給自足から商品経済へという考え方のこれまでの経済史の基本的な見方、根底にある捉え方でしょう。こうした人間に対する見方は、考えてみればずいぶんエゴイスティックで卑俗な人間観/実際はどうかというと、縄文時代から交易が行われているわけ2018/12/16
みのくま
8
網野善彦によると倭国と日本は同一ではない。西国と東国、東北は別の権力体制があった。面白いのが、畿内の倭人と東国の毛人の対立を、網野・石井両氏の東大系学者と、京大系学者の対立に重ねている点だ。そして、京大系は日本の稲作文化を自明視する傾向があるという。古代日本は律令を導入するに際し、隋唐では異なる水田を中心に据えた国家を目指した。だがそれは現実的に不可能にも関わらずである。この米に対する異常な執着は謎なのだが、それは儒教の農本イデオロギーによって強化され、歴史学においても「農業」が狭小に捉えられているようだ2021/11/18
kaz
8
今の歴史の教科書からは「士農工商」という表記は削除されて、代わりに「武士」と「百姓・町人」という表記に変わっているらしい。網野善彦さんらの歴史学者の成果の賜物だろう。歴史は決して化石のように固定されてはいない。一面的な理解だけでは物事の本当の姿は見えてこない。忘れ去られたようなもの、誰も見向きもしてこなかったことが重要な意味をもつこともある。律令制は明治維新によって完成をみたのではないか、という指摘が新鮮で面白かった。対談形式なので読みやすい。虚構の裏に隠された真実の姿を探る姿勢はエキサイティング。2019/06/03
lovekorea
3
歴史学というもののダイナミックさを感じることのできる対談本ですねー。江戸時代のことなんて、もうパーフェクトに解明されているかのような錯覚を抱いてしまいがちですが、よ~考えたらそんなわけないですもんな( ̄▽ ̄)2017/09/03
naof
3
棚田が残っているところというのは、伝統を大切にしようという意識が強かったからだというのはおそらくその通りだと思います。だけどそれだけじゃなく、実際それを維持して来られたことの裏には、農業以外の、商業や廻船などが発達するポテンシャルがあって地域全体として余裕があったという背景があるという点は、文化的景観を考える上でも重要なことだと感じます。2011/11/12