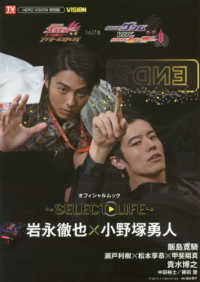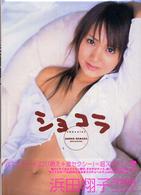出版社内容情報
『幸福論』が広く静かに読み継がれているモラリスト、アラン。卓越した哲学教師でもあった彼が平易かつ明快にプラトン哲学の精髄を説いた名著。
内容説明
『幸福論』のアランがプラトン哲学の精髄を詩的に解き明かす奥深いエセー。「ソクラテスの弁明」「クリトン」「パイドン」「饗宴」などの対話篇から自在に言葉を引き、その思想を語ってゆく。アランはプラトンに導かれつつ殺されて生かされ、プラトンはアランの鋭角的な精神によって変容されながら、自己の普遍性を損なわれることなく見事に開花する。モラリスト・アランの真骨頂たる一冊。
目次
第1章 ソクラテス
第2章 プロタゴラス
第3章 パルメニデス
第4章 イデア
第5章 洞窟
第6章 ティマイオス
第7章 アルキビアデス
第8章 カリクレス
第9章 ギュゲス
第10章 袋
第11章 エル
付 アリストテレスについてのノート
著者等紹介
アラン[アラン][Alain]
1868‐1951年。フランスの哲学者。本名エミール=オーギュスト・シャルティエ。高等師範学校卒業後、リセの教師となる。その哲学講義は学生たちの支持を受け、教え子からシモーヌ・ヴェイユをはじめとする哲学者を輩出している。65歳で教職を退き亡くなるまで執筆活動を続けた
森進一[モリシンイチ]
1923‐2005年。ギリシャ哲学者。元、関西医科大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しんすけ
19
若松英輔が紹介していたから気楽に手に取ってみたが、ぼくには敷居が高い本だった。 アランが当然のように語る言葉が、ぼくには当然でないことが多かった。たとえば、126頁の 「いわゆるプラトン的愛の何であるかは、誰でも自分は知っていると思っている。いや、だれでも知っていることだ。」 プラトニックラブについてだろうが、ぼくにはよく分からなかった。なぜならぼくにはプラトニックラブの経験がない。好きになった人の裸身をすぐに思い浮かべるぼくだからだ。 プラトンの全作品を読むだけでは、分からないことなのかもしれない。2022/08/28
さえきかずひこ
14
善く生きよ、というプラトンの命そのままをあらわさず、詩的かつ啓発的な修辞で閉じる11章がすこぶる印象的なプラトン入門書。本書の半分以上がイデアとは何かという記述に占められているところが素晴らしい。イデアについて語ることがプラトン哲学の核心に触れることをアランが確信していることが伝わってくるからである。訳文も淀みがなく読みやすいが、プラトンの極端な思想の数々が、彼の著作への解説を通じて心中に溜まるせいか、知的な重みは間違いなく読者に伝わるだろう。巻末の「アリストテレスについてのノート」もプラトン理解に有用。2018/08/29
うえ
8
「神学に関して言えば、数世紀にわたって神秘思想を育てるに足るだけのものを、プラトンが各所で語っていることを認めなくてはならぬ。たとえば、「テアイトス」において、賢者の仕事は、神をみならうことにあると言っているごとく。…ただそうした知慧は、もっと別の、もっとさし迫った、もっと積極的で、われわれにはるかに身近な他の知慧をも、覆っているのである。また、たとえキリスト教の神秘思想が…秀れた深さを現しているとはいえ、かつてプラトンがなしたほどに、われわれの心の奥の最も深い善や悪に触れていたとは、わたしは思わない」2022/06/08
かわかみ
5
アランにとってデカルトと同様にプラトンも大切な哲学者のようである。だが、イデア、洞窟、想起etc.を訓詁学として読み解こうとしたものではない。プラトンの考えたことを、もう一度、アランの中で消化して、捉えなおそうとしたもののようだ。プラトンが抱いてアランが再構成した考えは、言葉で直截に表現するには微妙で捉えがたい。それを掴まえようとすれば、詩的で回りくどい言い回ししかできないのだろう。だから、この本はプラトンを理屈で解説したものではない。読者も理屈で解ろうとしても無理なのだ。結局、私は煙に巻かれてしまった。2024/11/15
ちあき
0
アラン先生がプラトンを論じた一冊。訓詁学的な精緻さはないのかもしれない。倫理の教科書や資料集に書いてあるようなことはほとんど書かれていない。しかし深い読解。イデアを論じる意味がわからなかったのだが腑に落ちるものがあった。古典を読むときもこれほど自由闊達であっていいのだ、このように古典と向きあいたいと思わせる。最終章「エル」は『幸福論』に通じる味わいも。ギリシア哲学、とくに対話編が苦手でずっと遠ざけていたがこれは読んでみなければと思った。2010/12/21