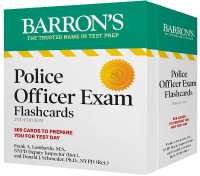出版社内容情報
内容は後日登録
内容説明
足利将軍邸を模した守護大名の館から、領地を一望する戦国大名の険しい山城、そして巨大な天守を誇った信長の安土城へ。中世から近世にかけて、城の形は大きく変化した。城跡調査からその変化を調べていくと、天下統一に向けて権力が再編成された日本中世の、新しい歴史像が明らかになってくる。本書は、城跡を歩く楽しさやコツなどフィールドワークの基礎から始まり、縄張り図から軍事戦略を読み解くポイントを伝授。さらにそこから見えてくる政治構造・地域社会の様相など、中世・近世史の謎をていねいに解明する。
目次
第1章 城にたどる歴史(戦国の城に分け入る;非観主義がつくる城 ほか)
第2章 城の探検(地図に城跡を読む;江戸時代の城と中世の城 ほか)
第3章 花の御所から戦国期拠点城郭へ(館と山城;歴博甲本洛中洛外図屏風 ほか)
第4章 城の語る天下統一(戦国以前の山城;戦国期拠点城郭の出現 ほか)
第5章 世界の中の日本の城(ナショナリズムと城;日本の城とヨーロッパの城 ほか)
著者等紹介
千田嘉博[センダヨシヒロ]
1963年生まれ。奈良大学文学部文化財学科卒業。大阪大学博士(文学)。文部省在外研究員としてドイツ考古学研究所、イギリス・ヨーク大学に留学。名古屋市教育委員会・見晴台考古資料館学芸員、国立歴史民俗博物館考古学研究部助教授を経て、奈良大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翠埜もぐら
14
「城郭考古学」から政治体制や物や人の流れ、文化文明の移り変わりを読み解き、文献史学や考古学と補完しあっていくというスケールの大きな話でした。最近読んだ中世史の中で、主と並び立つ程の力を持った家臣を排除できるかが、戦国大名として生き残れるかの一つの指針と言う話があったので、家臣を含めた住居群の形態から近世の大名への移行を読み解いていく話は、思わず「そーゆーことか」と腑に落ちてしまいました。「史観」が治世者に都合がいいように利用されることに関しての警鐘もとても共感しました。なんかTVのイメージとちょっと違う。2023/02/13
壱萬参仟縁
9
現代では、城そのものの存在はないが、もとはあったという場所がある。地域のシンボルとしての城。縄張りの語源は、築城の際、縄を張って堀(昨日の単語に出た)、曲輪(くるわ)の位置を決めたことに由来するとのこと(032頁)。動物にも縄張りがある。城のエリアもまた、存在感を示すには必要だったのだろう。地形図で城の存在感を確認できるとも指摘されている。053頁の岡山の金黒山城は面白い。これだけでどんな城か、想像する楽しみもあるが、評者にはイメージしにくい。室町の大不況(116頁~)。金閣寺のきらびやかさに反するかも。2013/08/26
のぶさん
3
テレビにもよく出演されている千田先生の本。タイトルから、具体的な城を巡った解説本かと思ったが、そういう部分は冒頭のみで、戦国時代に城郭がどのように進化したかを解説する本でした。単純に軍事的な変化を追うのではなく、領主と家臣の関係と縄張りの関係を指摘されています。想定とは違ったけれど、おもしろい内容でした。2021/08/12
ヘムレンしば
3
城巡りの楽しさと城の研究について。単なる軍事施設なだけではなく、権力の象徴だったり日常的な政治の場であったり。権力構造の変化から横並び的な曲輪群から上下構造の発達。地域住民との関わりから城下町の形成まで。さらに発展して海外のお城との比較も。難しそうな事をつらつら書いたけど、どれもとてもわかり易いです。元々城好きなので、なるほどー!と頷きながら夢中になって読みましたが、初めての人にも沢山読んで貰って、感想とかも聞いてみたいですねぇ。2021/05/25
おらひらお
3
2003年に刊行されていたものを2009年に収録したもの。タイトルにあるように城歩きのガイドブック。だけど、表紙の大阪城のような城ではなく、山の中で半ば埋没しかかった城が中心。いまだに名前の見知られ実態が不明なものが多いので、著者が説明する縄張図を用いた調査・研究は面白い視点と思う。最近、この分野の研究が増えてきています。2011/09/20