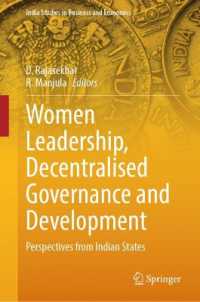内容説明
言葉とは何か?根源的で正解のないこの問いに真正面から取り組んだ、もっとも明晰な入門書。記号学・言語学研究の第一人者である著者が、言葉という永遠の謎に迫る。言葉はものの名前ではない。“表現”であり“意味”である。では“意味”とは何なのか―ソシュールをはじめとする言語学研究の軌跡を紹介しつつ、具体的な例を駆使し、平易な語り口で、伝えがたいことをできるかぎり噛み砕いて解き明かしてゆく。言語学、記号学、ソシュールに関心をもったとき、まず最初に読むべき一冊。述語解説、人物紹介、参考図書案内付き。
目次
1 言葉と文化
2 言葉とは何か(ホモ・ロクエンス;言語観の変遷;言語能力・社会の制度・個人の言葉;言葉の構造;言葉の状態と歴史;言葉と物;言葉と記号;言葉の単位;言葉の恣意性;言葉の意味と価値)
解説 丸山圭三郎・ソシュール・文学
著者等紹介
丸山圭三郎[マルヤマケイザブロウ]
1933-93年。東京大学文学部卒業。中央大学教授在職中に逝去。フランス文学・言語学・記号学専攻。ソシュールの原典の精緻な読み解きによって、ソシュール解釈に新地平を拓く一方、言語と文化をめぐって独自の思索を深め、日本の思想界に大きな影響を与えた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
(haro-n)
75
ソシュール以前の言語の捉え方は、ソシュールの言語学を知らなければ、むしろ当然な考え。そこから、ソシュールがいかに言語活動の仕組みを解き明かしていったかを丁寧に説明している。私は既に著者の『言語と無意識』を読んでいたので、分かりやすく読めた。3つのコノテーションの説明が、この本での収穫。解説では、丸山圭三郎氏を、ソシュールの言語学を「読む」にとどまらず言葉の創造的活動まで実践(「書く」)しようとした、日本の研究者の中では希有な思想家と紹介していた。解説者により、後学者のために参考文献が載っているのも良心的。2019/02/19
まこみや
51
丸山圭三郎の著作を何冊か必要があってほぼ40年振りに再読した。ソシュールの言うlangageとは人間だけがもつシンボル化能力であり、langueとは言語外の事物や概念を指す名前ではなく、象徴という〈コードなき差異〉の体系であって、つまりは実体のない関係からだけ成る体系だということだ。従って言語の習得とシンボル化能力は同時進行の現象であって、まさにメルロ=ポンティも言うように「言葉は認識の後にくるのではなく、言葉とは認識そのもの」なのである。と、このような理解でよろしいでしょうか。2022/10/25
zirou1984
50
とてもわかりやすく、丁寧にまとめられたソシュール入門書。言語というのは意味や対象を表現する二次的なものではなく、言葉は表現すると同時に意味付けるものであり、他の意味付けられた言葉との相互作用によって対象が恣意的に揺らぐものだと語り口調で解説してくれている。また、導入として言語と文化の話から入っていくが、そこでは言語とはひとつの文化的視点そのものであり、異なる言語を学ぶことは異なる文化からの視点を獲得することだと指摘することで他文化に「かぶれ」過ぎてしまうことへの警鐘をきちんと鳴らしていることも信頼できる。2014/05/27
かんやん
43
ソシュール入門書。意識そのものを意識化することが難しいように、言葉を言葉で分析することにはメタレベルのややこしさがつきまとう。言葉は単なるモノの名前ではなく、混沌とした(或いは連続した)現実を、カテゴライズして整理する、つまり人間化する機能を持つ(故に思考は言語に囚われている)。ランガージュ、ラング、シニフィアン、シニフィエといった概念をわかりやすく説明してくれるので、助かる(所記、能記なんて悪訳があったなあ)し、レヴィ=ストロースが如何にこの言語学者に影響を受けたわかる。自分もちょっと誤解があった。2019/11/05
1959のコールマン
40
☆5。身近すぎてかえってじゅうぶん分かっているような錯覚を起こす「言葉」というモノ。この本はソシュールを手がかりに丸山圭三郎がこの「言葉」を十二分に分析し、解き明かしている。もちろんこれはイントロダクションにすぎないのであって、主著の1つ「ソシュールの思想」にもっと詳しく分析されている。文章自体は難しくない、否、よくぞこれだけ分かりにくい概念をこれだけ分かりやすく書けたものだと感心、いや感謝している。言語に興味のある人、ソシュールを読みこなしたい人、丸山圭三郎の思想に関心のある人、必読の書である。2019/08/10
-

- 電子書籍
- ぽっちゃり悪女のレストラン【タテヨミ】…