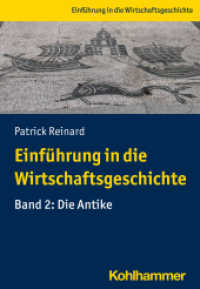内容説明
人智学協会設立までの3年間、シュタイナーは神智学協会年次大会で4日間ずつの連続講演を行った。その各年のテーマが、「人智学」「心智学」「霊智学」である。これは各々、シュタイナー人智学の体・魂・霊の三分法に対応するもので、それぞれが感覚論、判断・感情論をへて、霊視・霊聴を通じた存在へと成就する道が精査される。アリストテレスからブレンターノにいたる伝統的「霊魂論」の批判的検討に加え、なぜ心智学が精密科学の方法によっては証明できないものであるかなどを説き、神智学運動を理論的に基礎づけた、シュタイナー成熟期のトリロジー。
目次
1 人智学(ベルリン一九〇九年十月二十三日‐二十七日)(人智学と神智学並びに人間学との関係―人間の諸感覚;人間の超感覚的な本性から諸感覚が生じる;高次の諸感覚―人体におけるエネルギーの流れと器官形成;人間の体と動物の体―言語感覚と概念感覚の育成―純粋思考―記憶)
2 心智学(ベルリン一九一〇年十一月一日‐四日)(魂を構成する諸要素―判断と愛憎;人間の魂の諸力の対立;外的な感性と内的な感性―感情と美的判断―感情と意志;意識―自我観念と自我の力―ゲーテとヘーゲル)
3 霊智学(ベルリン一九一一年十二月十二日‐十六日)(フランツ・ブレンターノ―アリストテレスの「霊」理論;神智学から見た真理と誤謬;霊視と想像力―霊的合一と良心―霊聴の中での霊視と霊的合一の統合こそが存在を成就させる;文化の発展と自然の法則、その中に生きる人間―家としての身体―生まれ変ろうとする意志)
著者等紹介
シュタイナー,ルドルフ[シュタイナー,ルドルフ][Steiner,Rudolf]
1861‐1925。オーストリアの哲学者。アナーキズム系の評論活動を行った後、40代で神智学協会ドイツ代表として活躍し、表現主義運動に影響を与えた。1913年人智学協会を創設し、科学、芸術、教育、医療、農業の分野にいたる人智学運動を展開する
高橋巖[タカハシイワオ]
東京生まれ。慶応義塾大学大学院博士課程修了。1973年まで同大学文学部哲学科、美学・美術史教授。現在、日本人智学協会代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。