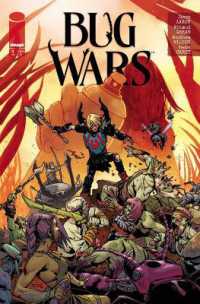内容説明
21歳での処女出版『ランスの大聖堂』と、第2次大戦前後の重要テクスト選集。1918年の表題作は信仰時代の青年バタイユの貴重な証言であり、すでに聖性における究極の脱自という生涯のテーマがうかがわれる。ほかに、信仰放棄後の地母神と大地の闇に光を当てるディオニュソス的母性論、消尽のエネルギーを論じるプロメテウス=ゴッホ論など『無神学大全』の思索の原型から、戦後のシュルレアリスムへの逆説的擁護や実存主義との対決、凝縮されたイメージに神を透視する論考など17のテクスト。バタイユ最初期から中期のエッセンス。
目次
1 一九一八(ランスのノートル・ダム大聖堂)
2 一九三七‐四〇(悲劇=母;髪;プロメテウスとしてのファン・ゴッホ;天体 ほか)
3 一九四六‐四八(半睡状態について;アンドレ・マッソン;よみがえるディオニュソス;取るか棄てるか ほか)
著者等紹介
バタイユ,ジョルジュ[バタイユ,ジョルジュ][Bataille,Georges]
1897‐1962年。20世紀フランスの思想家。第2次大戦前、美学・考古学の雑誌「ドキュマン」、左翼政治団体「民主共産主義サークル」、宗教的秘密結社「アセファル」などで活躍。大戦中『無神学大全』を発表。戦後、書評誌「クリティーク」を中心に広範で尖鋭な論陣を張る
酒井健[サカイタケシ]
1954年、東京生まれ。東京大学文学部仏文科および大学院修了。パリ大学でバタイユ論により博士号取得。法政大学文学部教授。『ゴシックとは何か』(サントリー学芸賞)など。バタイユの訳書も多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
∃.狂茶党
しゅん
春ドーナツ
ラウリスタ~
こうず
-

- 和書
- 販売促進戦略事典