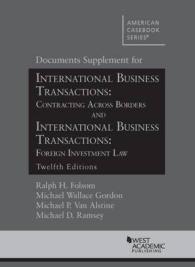内容説明
都心の地下は骨だらけ。東京の地面の下には人骨が描くもう一つの江戸・東京地図が封印されている。―実際、都心では大きな工事のたびに夥しい骨や墓の跡が発見されている。「まさかこんなところが墓地だったとは」。でも気付かないのも当たり前。なぜなら、かつて寺は「人捨て場」と一体で、寺の頻繁な引越しはウワモノだけの移転で済まされ、骨はかまわず打ち捨てられていたから。この「骨だらけ」という事実から、古い江戸の姿、都市造営、葬儀と埋葬など、歴史、地理、民俗、宗教にまたがるさまざまな事実を、豊富な資料やデータを駆使して浮かび上がらせた異色の都市史。
目次
第1部 東京の骨(日本人の死体観;死体と骨の間;江戸の寺院;骨の見つかり方;江戸の寺院のデータ;骨の発見の時代差)
第2部 東京の怨霊(はじめに―「やしろ」の改称;明治の宗教改革;神社号の誕生;京都との比較;神の定義について ほか)
著者等紹介
鈴木理生[スズキマサオ]
1926年、東京生まれ。千代田図書館勤務、東京都市史研究所理事を経て現在に至る。都市史研究家。地形学・考古学の視点から実証的に都市史をとらえ直し、都市の形成と変遷、流通、交通体系など多角的に論じている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
32
『江戸はこうして造られた』読了後に読み始めたので、かなり重複する部分はあったのだが、墓地の跡地に建てられた学校の怪異が当然のごとく書かれており、あとがきでも骨に起因するナニカの存在を肯定するなど、前著とは趣きが変わっているが自分好みの本であることに違いはない。江戸人が幕府の開発に追われて打ち捨てざるを得なかった土葬の屍。その祟りから逃れるべく大家は自宅敷地内に稲荷社を建て、町人は辻々にお稲荷様を祀ったという説に何だか納得してしまう。開発の陰で闇に葬られた江戸文化に、文化財保護法の功罪も考えさせられた。2015/10/13
ドナルド@灯れ松明の火
30
これは掘り出し物だった。江戸時代の考証は普通は地上だけだが、本作は地面の下の考証である。江戸城の拡張や大名屋敷を作るために寺をどんどん移転させた。そのためお墓の下は放置して移転した為、現東京の地下には数多くの骨が眠っている。葬儀と埋葬等、地理・民俗と宗教の関係が良く分かった。明治になってから廃仏毀釈時の火葬の禁止等知らなかった話が盛り沢山。圧倒的に寺が優勢で神社を境内に祀ってあったものが明治からは神社は分離させられた。明神と権現の違い等目から鱗の情報も満載。鈴木さんの作品を追っかけていきたい。 お薦め。2014/09/02
ふろんた2.0
7
江戸時代に急速に発達した現東京は、開発のために寺社を強制的に移動させたが、墓の下はそのままであった。江戸時代の闇の部分を見た気がする。2016/12/14
紫暗
5
江戸、つまり東京は徳川家康が収めるようになった当時は今のような大都市だったわけではなく、家康が天下をとってから急速に発展した町だということを改めて実感しました。そして、その急速な発展が、寺社や墓の移転を急がせ、数多くの遺骨を地中に残したまま、その上に発展していったのだということも初めて知りました。江戸だけではなく、都市開発について考えさせられる一冊でした。2014/05/26
Akito Yoshiue
3
地味なテーマではあるが、筆者の文章力もあって非常にスリリングな論考になっている。筆者のほかの作品も読んでみたい。2015/06/19
-
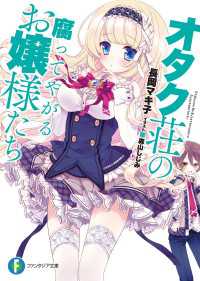
- 電子書籍
- オタク荘の腐ってやがるお嬢様たち 富士…
-

- 和書
- 図解薬剤学