内容説明
知識とは一体何か。古代ギリシアで、初めて生まれた本格的省察。ソクラテスは、幾何学の天才であった若者テアイテトスを相手に、人間の経験のあらゆる領域に及んで、知識とは何かを問う。問うのみで答えを示さないソクラテスは、「知覚」「真なる判断」「真なる判断に説明が付け加わったもの」という、テアイテトスの精神が生んだ“子どもたち”を次々と吟味し検討した後、冷酷に否定する。認識と意味に関して西洋哲学草創期にあらわれたこの論考は、今もなお、読者に哲学的思考を促し、考えるための刺激となる数々の議論と、挑戦しがいのある難問に満ちている。
目次
第1部 知識の第一定義「知覚が知識である」の提示、展開、批判
第2部 知識の第二定義「真なる判断が知識である」の提示と批判
第3部 知識の第三定義「真なる判断に説明が加わったものが知識である」の提示と批判
訳注
補注1 判断のポイント
補注2 構造化された能力
補注3 「名と名の織り合わせ」(『テアイテトス』)から「名と述語の織り合わせ」(『ソピステス』)へ
著者等紹介
プラトン[プラトン][Platon]
紀元前428/427‐348/347年。古代ギリシアの哲学者。初め詩人志望であったが、ソクラテスに出会い哲学の道を歩む。ソクラテスの裁判と刑死の後各地を遍歴して、アテナイ郊外に学園アカデメイアを創設。著作は、西洋哲学史上初めて“全集”として残る。それらは戯曲形式で書かれ、「対話篇」と称される
渡辺邦夫[ワタナベクニオ]
1954年生まれ。1982年、東京大学大学院比較文学比較文化専門課程博士課程単位取得退学。現在、茨城大学人文学部教授。古代ギリシア哲学専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェルナーの日記
ありす
helecho
-
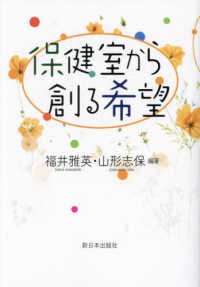
- 和書
- 保健室から創る希望






