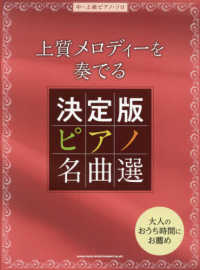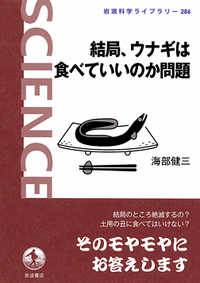内容説明
ピンホールを通して外界の風景を捉える装置、「写真鏡(カメラ・オブスキュラ)」。カメラの前身になったといわれるこの機器を通すと、人間の視覚が捉える映像を、客観的に写しとることができる。ダ・ヴィンチやフェルメールなど西洋の画家たちはこの写真鏡を用いて下絵をトレースし、日本では洋風画の先駆者らが取り入れた。カメラマンでもある著者が、人間の目に映った映像がどのように絵画作品になっていったのか、写真鏡をとおして東西美術史を検討しなおす。
目次
序章 「映像」とは
第1章 「写真鏡」とは何か―西欧の写真鏡の通史
第2章 「写真鏡」の渡来
第3章 遠近法による視覚の変革―洋風画の胎動
第4章 遠近法の浸透―蘭学の隆盛と洋風画・銅版画の成立
第5章 日常化した遠近法―洋風画の消化
第6章 写真の発明―写真鏡から写真機へ
著者等紹介
中川邦昭[ナカガワクニアキ]
1943年京都市生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。フリーカメラマン。日本写真家協会、民族芸術学会、日本写真芸術学会、日本ペンクラブ各会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
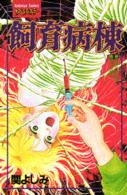
- 和書
- 飼育病棟 フレンドKC