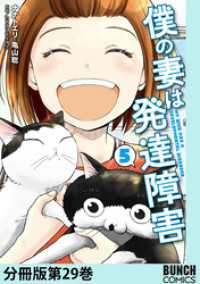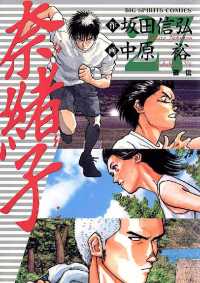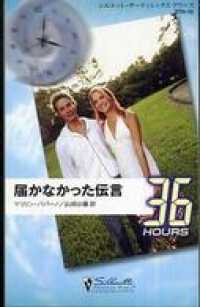内容説明
現在の象徴体系、認識体系研究の先駆けとなったフランス社会学黄金期の著作。論文「死の宗教社会学」を併録する。
目次
死の宗教社会学―死の集合表象研究への寄与(あいだの期間;最終の儀式)
右手の優越―宗教的両極性の研究(有機体の非対称性;宗教的両極性;右と左の特徴;両手の機能)
著者等紹介
エルツ,ロベール[エルツ,ロベール][Hertz,Robert]
1882年生まれ。1904年、エコール・ノルマル卒業。1915年、第一次世界大戦の東部戦線マルシェヴィルで33歳の若さで戦死。フランスの社会学者、社会人類学者。デュルケム門下の秀才で、1915年の悲劇がなかったら、師と肩を並べる研究者になったであろうと言われている
吉田禎吾[ヨシダテイゴ]
東京大学名誉教授
内藤莞爾[ナイトウカンジ]
九州大学名誉教授
板橋作美[イタバシサクミ]
東京医科歯科大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ラウリスタ~
18
死者の埋葬が非常に複雑であるのは単に死体への恐怖によるのではない、その証拠に死者が幼児であったり、未亡人、通りすがりの異人、すでに耄碌した老人、首長だったりという条件によって死体の扱い方が変わる。遺体がきちんと段階を踏んで、安全なものへと移行するのを見届けるのが数度に渡る(時に数年間かけての)葬儀。右手の優越(というか左の不浄)は、西洋語では語彙のレベルで徹底されているが、それが全世界的に普遍的な現象だとエルツは考えているが、それには反論の余地があるようだ。2016/08/13
藤月はな(灯れ松明の火)
13
1年前の文化人類学の授業でエルツの「左右の優劣」を紹介され、大学の図書館にコンパクトなサイズで置かれていたので読みました。左右の優劣ですが日本では左大臣と右大臣の例のように逆転する場合もあるので「左は劣、右は優」というのは白黒はっきりつけたがるヨーロッパ的考えとも言えます。また、マージナルなものの場合は各自の文化でどのような捉え方をするのかも興味深い所です。社会へ存在の喪失を精神にも完全に受け入れる段階的葬儀は日本でも通夜、葬儀という例にも通じるのではないかと思います。2012/11/06
gunji_k
2
宗教をいくら批判しようとも、死ねば葬送を行わないわけにはいかず、その儀礼には必ずフィクションが紛れ込み、それはまさに宗教と呼ばれるものになる。死ねば関係ない、などと幼稚な戯言をいう前に、本書収録の『死の宗教社会学』を。死の絶対的な恐怖に呑まれて白けることなく、人類は葬送の儀礼とフィクションの更新を行ってきたし、やり方は一つじゃないのだ。2011/07/25
★★★★★
2
今読むと一見たいしたことない小論のように思えますが、1907年という発表年と現代に通じる問題意識を考え合わせるとその卓抜さが実感されます。2009/01/04
bossa19
1
死の宗教社会学ではただの観察の羅列に近く宗教観が社会制度などにどう影響するかまであまり考察してないのが残念。結びに少し書いてるけど。キリスト教的価値観から見た他の宗教についての観察の仕方だからなのか違和感も感じる。右と左については面白いことは何もなかった。(読了:2001/11/06)2003/01/01