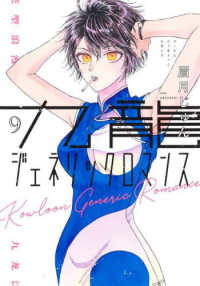内容説明
恐れることはない、とにかく「盗め!」世界はそれを手当たり次第にサンプリングし、ずたずたにカットアップし、飽くことなくリミックスするために転がっている素材のようなものだ―「作家」と「作品」という概念およびその成立の正当な基盤とされる歴史性と美学、ひいては「近代」の起源そのものの捏造性を看破、無限に加速される批評言語の徹底的実践とともに、まったく新たな世界認識のセオリーを呈示し、その後のアート、カルチャーシーンに圧倒的な影響を与えた名著。「講義篇」増補を含む。
目次
-01 シミュレーショニズム 講義篇
00 シミュラクルの戦略(シミュラクルの戦略;サンプリング ほか)
01 シミュレーション・アート(非整数次元の芸術;サンプリング・アート ほか)
02 ハウスミュージック(ハウスミュージック;サンプリング/カットアップ/リミックス ほか)
03 ポスト・ヤルタ体制下の反美学(マシーン・エイジ;ポップの死滅 ほか)
著者等紹介
椹木野衣[サワラギノイ]
1962年、秩父市生まれ。美術評論家。現在、多摩美術大学助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
57
以前から読みたかった音楽美術評論。表題の通り、ボードリヤールの概念や現代思想の用語を駆使して、80年代ごろの美術、音楽(ハウス・ミュージック)の意義などを論ずる。馴染みのある演奏家や曲などがでてきて懐かしく、内容的にも納得のいく部分がある。過剰なジャーゴンと断言が絡まるこの文体は面白い。かなり主観が(客観的な内容を目指す本は大体面白くないものだが)強いように感じられる。畳み掛けるような語りはアジ演説のようだ。評論芸の極限ではないかと。2017/05/30
zirou1984
38
キーワードは「サンプリング/カットアップ/リミックス」。80年代に広まった美術運動、シミュレーショニズムの考えをポピュラー音楽に援用していくその切り口はウィルス的感染力を感じさせる。本編は20代の頃に執筆されたが故のレトリック過多な部分も目につくが、増補において加えられた最初の講義編が導入として優れており現代アート入門としても機能している。「盗め!」という発売当時のメッセージは現代において「コピれ!」と言い換えるのが相応しいだろう。IT技術の発達で世界はこんなにもコピー&ペーストで満ち溢れているのだから。2015/07/14
踊る猫
31
該博な知識があり、かつその知識をいい意味で野蛮にかつ柔軟に使いこなすセンスにも長けており、読むにつけ唸らされ引き込まれる。椹木野衣の視線はしかしそうしてたんに美術や音楽を分析するのみにとどまらず、そうしたフィールドを可能にしている資本主義についても目配りを効かせており、したがって(語弊を恐れずに言うなら)「政治的」な書物でもあるなと感じ入る。先行するニューアカの知識人とはまた違った種類の戦略性をベースに(そして後進の知識人の持つオタク的なノリとも異なった皮膚感覚で)、椹木の分析はこの1冊で鋭い冴えを見せる2025/09/09
しゅん
17
引用ではなくサンプリングによって美術史をメタ的に問い直すこと。ハウスミュージックのリミックスの大量生産がウィルスのシミュレーションとなること。ネオアートとアンダーグラウンドミュージックに触発されて書かれたこの刺激的な批評集は今どのように読まれるべきだろうか。インターネットとSNSの大量拡散が日常風景となって時代には、シミュレーショニズムの感染力はすっかり解毒されているだろうか。今の私には仮の回答すら持てないが、少なくとも当然の風景を破り捨てる力が存在した時代、その熱量の記録を読むことは決して無駄ではない。2017/04/22
サイバーパンツ
14
時代背景から察するに「歴史の終わり」や浅田彰、後はタイトルで察する通りボードリヤールなんかの影響が強い。現代美術からハウスミュージックまで、かなり広範囲の芸術を批評のジャーゴンを(過剰装飾ぎみに)使って、独自の歴史認識のうちに落とし込んでいく様は雑多ながらも美しく、まさに本書が説明したシミュレーショニズムの実践のようである。またそれと同時に、今後の「日本=悪い場所」論に通ずるような、著者の問題意識が随所に現れており、彼の思想的な一貫性を強く感じた。2017/05/12
-

- 洋書電子書籍
- ソーシャルワーク:理論と実践(第4版)…