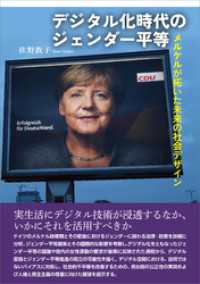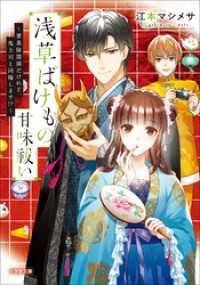内容説明
この世の如何なる酸鼻であろうと許容し、愚劣で、無意味な生存を肯定する。此岸を「彼方」として生きる明確な意志さえあれば、人生は「甘美」な奇跡で満ち溢れる。柄谷行人の「営みとしての批評」を炙り出し、破壊的な衝動と理不尽な力を村上春樹の小説に読みとる。芥川の「憎悪と笑い」、谷崎の「虚無的な決意」、日本の弱き神の脆き夢としての『万葉集』…、さまざまな文学を巡りながら、およそ倫理や社会道徳に迎合することなく、世俗の最も愛情こまやかな絆からさえ逃れ出る、耽美への意志が穿つ現世の真実。平林たい子賞受賞の挑戦的な評論集。
目次
批評私観―石組みの下の哄笑
柄谷行人氏と日本の批評
ソフトボールのような死の固まりをメスで切り開くこと―村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第一部、第二部
放蕩小説試論
芥川龍之介の「笑い」―憎悪の様式としてのディレッタンティスム
精神の散文―佐藤春夫論
水無瀬の宮から―『蘆刈』を巡って・谷崎潤一郎論
木蓮の白、山吹の黄
斑鳩への急使―万葉集論
ほむら、たわぶれ―和泉式部論
さすらいたまふ神々―生きている折口信夫
日本という問い
生活の露呈―河井寛次郎論
甘美な人生
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
12
1995年に発表された最初の文芸論集。福田はこの世界にあるもの、酸鼻も不可解も醜悪も全てをまずは受け止めて認識するべきだという倫理を基礎に置いている。柄谷行人の文の「上演性」に対する批判も、事前に用意されたシナリオにない「外部」(柄谷自身が好む言葉)を排除していると考えるから。最初に事実誤認を指摘し、しかしそれこそが美点であると反転させ、本当の欠点は美点の奥にあるとさらにひっくり返す柄谷論の構成はマジで気持ちいい。そして、福田の面白いところは、柄谷的「外部」に「日本」という(厄介な)名を与えた点にある。2021/04/08
しずかな午後
9
一応、古典から現代の作品までを扱った文芸批評の本なのだが、こんなに邪悪なテキストも他に無いんじゃないかと思わせる、異様な魅力をたたえている。芥川龍之介の自死を芥川の最後の作品として賞玩する「芥川龍之介の「笑い」」、谷崎潤一郎や村上龍の作品から弱者を虐げることの愉楽へ筆を進める「放蕩小説試論」、アメリカ兵が記念に持ち去った硫黄島の日本兵の頭蓋骨から同島で戦死した折口信夫の恋人・折口春洋を連想する「さすらひたまふ神々」など、どれも本当にその突き抜けた「悪さ」にクラクラする。素晴らしい一冊だった。2025/01/17
ダイキ
6
福田和也の第一文芸批評集。福田和也はその初期、つまり「ひと月百冊読み、三百枚書く」なんて事をし出す前は凄かったという事をよく聞くけども、確かにこれほど惚れ惚れする文章は滅多に読んだ事がない。惚れ惚れといっては聞こえは良いものの、それは段々と寒気にすり替わってゆくようなもので、外貌の論理こそは彼の敬慕する保田與重郎のそれでも、懐胎している思想は川端康成的な“魔”に断然近く、単に審美的な趣味から好ましく思っていなかったにすぎない福田の肖像が、本物の悪魔のように見えてきて薄気味悪くなってくる。2018/04/29
aquirax_k
3
必読。死ぬほど面白い。
この世はもう時期おしまいだ
1
柄谷批評を解体せしめる「柄谷行人氏と日本の批評」は圧巻のひと言。2015/05/19