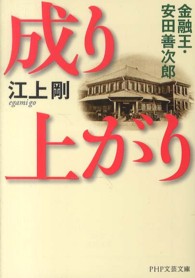内容説明
人類にとって宗教的現象とはいったい何か、人類史という壮大なスケールのなかでその展望を企てた本書は、20世紀を代表する宗教学者・エリアーデが最晩年に遺した畢生のライフワークである。この古今未曾有の偉大な業績は、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教といった個々の宗教の理解を助けるばかりでなく、人類が創造した宗教そのものの姿を見事に描きだしている。文庫版第4巻は、ナーガールジュナまでの仏教、ヒンドゥー教の総合、ユダヤ教の試練、ヘレニズム時代におけるシンクレティズムと創造性、キリスト教の誕生、帝政時代の異教グノーシス派、神々のたそがれまでを収める。
目次
第23章 マハーカーシャパからナーガールジュナにいたる仏教の歴史とマハーヴィーラ後のジャイナ教
第24章 ヒンドゥー教の総合―『マハーバーラタ』と『バガヴァッド・ギーター』
第25章 ユダヤ教の試練―黙示からトーラーの称賛へ
第26章 ヘレニズム時代におけるシンクレティズムと創造性―救済の約束
第27章 イランにおける新たな総合
第28章 キリスト教の誕生
第29章 帝政時代の異教、キリスト教、グノーシス派
第30章 神々のたそがれ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
44
キリスト教の誕生からが面白く読めました。やはり自分に馴染みのある宗教だからでしょうね。2022/12/10
塩崎ツトム
14
自分の世界史の知識の中にある、ユダヤ教→キリスト教→ローマ国教化の間にある断絶を埋める。キリストの登場までに、ユダヤ教の宗派でどんな紆余曲折があったのか?グノーシス派とは?マニ教にズルワーン教。聖パウロの役割。宗教史は決して直線的なものではなくて、沢山の統合と分裂を繰り返した、宗教的豊穣な時代があった。2024/08/21
Copper Kettle
6
しかし相変わらずインドに関する章は理解ができない、ある程度の知識が前提となっていると思う。なんとなくの理解だけどヘレニズムによってギリシア哲学が流入してくることでユダヤ教も危機を迎え、試行錯誤してその危機を脱したということかな、それが律法=トーラーの称揚ということのようだけど合ってるかな。残り100ページでようやくキリスト教が誕生する。比較的新しい宗教ってことだね。だいぶ読みやすくなった。最後の1940年の出来事、密儀の地エレウシスに止まったバスに乗っていた老婆のエピソードはなかなか印象的。2023/01/15
roughfractus02
5
脱魂体験(ekstasis)は総合なる地平を創造するが、多様性を受け入れて当初のモチーフから変容を遂げる総合と、当初のモチーフを維持して多様性と対立する総合に分岐する。前者は仏教に見られ、後者はヘレニズムの多様性と対立するユダヤ教内部にキリスト教を萌芽させる。一方、両者には共通の矛盾があり、多様性は善悪の葛藤に集約されて共に終末論思想を作り出す原動力となる。神と悪魔を総合する仕方に注目した本書は、農耕的なインド・ヨーロッパ語族と遊牧的なセム語族の脱魂の質的な違いをイエスの「神の国」に関する言葉にも見出す。2021/07/03
kakeruuriko
1
関係ないけど面白そうな話やりそうになると「~については本旨に寄与するところがないのでここでは触れない」とかで片付けて進む、丁寧2020/03/07
-

- 洋書電子書籍
- Lubrication and Dyn…