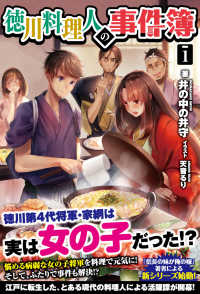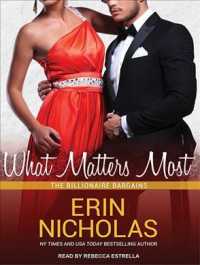内容説明
資本主義の逆説とは貨幣のなかにある!『資本論』を丹念に読み解き、その価値形態論を徹底化することによって貨幣の本質を抉り出して、「貨幣とは何か」という命題に最終解答を与えようとする。貨幣商品説と貨幣法制説の対立を止揚し、貨幣の謎をめぐってたたかわされてきた悠久千年の争いに明快な決着をつける。
目次
第1章 価値形態論
第2章 交換過程論
第3章 貨幣系譜論
第4章 恐慌論
第5章 危機論
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kawai Hideki
44
「貨幣とは何か」という抽象的な問いに対して、マルクスの『資本論』を下敷きにしながら、抽象的に論じた本。前半は難解で読むのに骨が折れるが、後半の貨幣系譜論あたりから、話が具体的になってくるのと、著者の修辞的言い回しに慣れてくるので読みやすくなる。1993年の出版だが、ビットコインが単なるビット列で後ろ盾となる国家もないのに貨幣として流通する理由、アベノミクスがインフレターゲットを設定する理由、世界的なハイパーインフレの可能性などについて、いろいろと示唆があって面白かった。2014/01/03
ころこ
40
労働価値説を否定しているように、マルクスが言ったことに囚われない、それでいてマルクスの可能性を引き出した議論です。「後記」で軽く触れているように、貨幣は言語そのものであり、貨幣の誘惑はそこに言語にはない数字による価値づけという機能が加わっているからです。それ故、循環が可視化されるのですが…なぜ言語に言及するかというと、『批評空間』で連載していた経緯から柄谷行人を意識しているからでしょう。規則の決定不可能性は貨幣と、言語でいえばウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」、恐らくここにゲーデルが追加されるはずです。2021/01/11
逆丸カツハ
26
ケインズ全集を読んでいて気になったところがあり、再読。やはり素晴らしい。自分の書いたエッセイは貨幣論をその可能性の中心において読むということをしていたのではないかと思う。2024/03/16
やまやま
20
マルクスさんは神と崇めなければなかなかに面白い社会経済学者であると思います。財物やサービスは一人一人にとっての使用価値がある一方で、それを「交換」するための尺度として貨幣の役割が認識されるようになった、という命題として受け取ることができ、著者の意図を十分に理解していないかもしれませんが、納得できました。「貨幣は貨幣として使われるものである。」という木で鼻を括ったまとめ方も、それまであった貨幣商品説や貨幣法制説などの整理方法では貨幣を定義するのに不十分であろうという意図と理解しました。2020/10/17
masawo
18
マルクスの資本論の参考書として購入。貨幣価値の問題から始まり、恐慌→ハイパーインフレを経由して辿り着いた結論はそこまで意外性はないが、経済学の要点をざっとおさらいできるという点では有用だと思う。接続詞の「すなわち」を多用しすぎる感が若干あり。2021/01/07