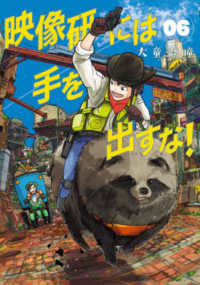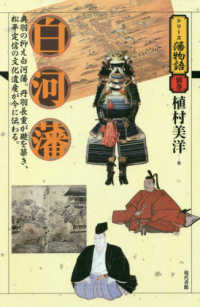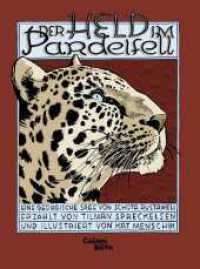内容説明
開国の時期における、自我の原則と所属する集団・制度への忠誠との相剋を描き、忠誠と反逆という概念を思想史的に位置づけた表題作のほか、幕藩体制の解体期から明治国家の完成に至る時代を対象とした思想史論を集大成。『古事記伝』のなかに、近代にいたる歴史意識の展開を探る「歴史意識の『古層』」を付す。
目次
忠誠と反逆
幕末における視座の変革―佐久間象山の場合
開国
近代日本思想史における国家理性の問題
日本思想史における問答体の系譜―中江兆民『三酔人経綸問答』の位置づけ
福沢・岡倉・内村―西欧化と知識人
歴史意識の「古層」
思想史の考え方について―類型・範囲・対象
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ばんだねいっぺい
23
なかなかの難物でしたが、きらりと光る一文が随所にあって楽しい読書でした。それにしても思想史は、考えてきたことを考えるややこしく重要な学問であると感じました。なぜ、忠誠するのか、反逆するのか、松陰は、ウケるのに象山は、なぜ、ウケないのか。今と繋がっていると思いました。2025/10/25
本とフルート
6
読書とは元来孤独な営みだと思っていたが、丸山眞男の広範な知性に相対するのは一人では到底不可能だと悟った。国学から中江兆民に至るまで、日本の思想のあり方というものに真っ向から対峙する姿勢に圧倒された。『権力政治に、権力政治としての自己認識があり、国家利害が国家利害の問題として自覚されているかぎり、そこには同時にそうした権力行使なり利害なりの「限界」の意識が伴っている。これに反して、権力行使がそのまま、道徳や倫理の実現であるかのように、道徳的言辞で語られれば語られるほど、そうした「限界」の自覚は薄れていく」2024/04/10
politics
6
武士社会から二十世紀ごろにまで渡って忠誠と叛逆という武士的なエートスが如何に変容して来たかを問う表題作、『古事記伝』や頼山陽らのテキストを題材に「つぎつぎになりゆくいきほひ」という歴史意識の解明を目指した「歴史意識の古層」、 思想史の方法論を平易に語った「思想史の考え方について」などの八つの論文が収められた氏最後の著作。個々の点では既に乗り越えられた内容のもの多いが、「古典」としての魅力は失われておらず、所謂「夜店」ものよりこちらの作品の方が私自身は好きだと感じる。何度も読み返す事になる傑作の一つだろう。2022/09/11
NICK
6
ある事物に忠誠する、というとき忠誠の仕方には二つある。一つはその事物の抽象的な原理に忠誠すること。もう一つは眼前のその事物そのものに忠誠すること。表題論文のみならず各所で丸山眞男が問題にしていたのはこのことで、前者は原理に忠実な以上現状への反逆の契機を獲得しうるが、後者は現実に対し「ズルズルベッタリ」の関係になりやすい。忠誠の対象を抽象的身体(原理)か具体的身体かに求めるのは大澤真幸の「第三者の審級」論を思い起こさせる。日本の歴史意識に「つぎつぎとなりゆくいきほひ」を見出す『歴史意識の古層』もマストリード2016/03/04
obanyan
5
やっぱり「忠誠と反逆」「歴史意識の『古層』」が難解なるも抜群に魅力的。前者は、盲目的服従として捉えられがちな「君、君たらずとも、臣、臣足らざるべからず」という封建的主従関係の中に、主君を諫め「真の君」たらんとする能動的な「諫争」の契機を見出す、画期的な論考。後者は「古事記」「日本書紀」の読解から、「執拗な持続低音」として響き続けてきた「つぎつぎになりゆくいきほひ」という日本人特有の思惟様式を抽出する。講演録も含め、「夜店」にはない、日本政治思想史研究という丸山自身の「本業」の魅力が存分に詰まった一冊です。2016/07/17