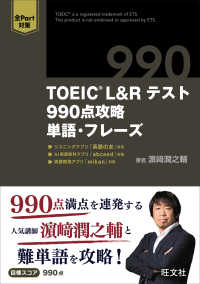内容説明
「われわれの文化の基盤は過剰、生産過剰にある。その結果、われわれの感覚的経験は着実に鋭敏さを失いつつある。…われわれはもっと多くを見、もっと多くを聞き、もっと多くを感じるようにならなければならない」。「内容」や「解釈」を偏重するこれまでの批評に対し、「形式」を感受する官能美学の復権を唱えた60年代のマニフェスト。「批評の機能は、作品がいかにしてそのものであるかを、いや作品がまさにそのものであることを、明らかにすることであって、作品が何を意味しているかを示すことではない。解釈の代わりに、われわれは芸術の官能美学を必要としている」。
目次
反解釈
様式について
模範的苦悩者としての芸術家
シモーヌ・ヴェーユ
カミュの『ノートブック』
ミシェル・レリスの『成熟の年齢』
英雄としての文化人類学者
ジェルジ・ルカーチの文学論
サルトルの『聖ジュネ』
ナタリー・サロートと小説〔ほか〕
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zirou1984
45
自分にとってソンタグの文章を読むのは、己の背筋をきちんと伸ばすことに似ている。それは詭弁や小難しいだけの観念に振り回されることなく、自身の五感から紐解かれる感性に、身体から立ち昇る知性に向き合うということだ。あらゆるものがカテゴライズ化され、分類することで何かをわかった気になった身を猛省したくなる。真っ直ぐに対象を捕え、ごまかしのない文章はこんなにも世界の欺瞞を剥ぎ取り、剥き出しの姿を暴き立てる。ソンタグの言葉には、本当の知性のみが持ちうる色気がある。それは理性が持ちうる美しさといってもいいだろう。2014/11/15
ラウリスタ~
9
最初の二つの論文は、この論文集がどんなことを扱うのかということについて語っているが、非常に面白い。芸術作品に対する知性の逆襲としての「解釈」、どんな「形式」にも「内容」などというものを探し求める試みへの批判。ただマルクス主義的批評などがおそらくとっくの昔にどっかに消え去った現代からすれば仮想敵はもういないのかもしれない。アメリカ人にも、アメリカ文学のくだらなさをしっかりと認識している人がいるようで安心した、この地ではジャーナリストが書いた標題音楽の文学版が文学作品としてのさばっているのだ。2015/01/09
Sunlight
8
50年前の著作なのでさすがに古さを感じる。批評の対象も一昔前の芸術家の作品で、読んだり観たりしたことがあるのはカミュ、サルトル、レヴィ・ストロース、ゴダールあたりだった。それでもなお本のタイトルである「反解釈」と「《キャンプ》についてのノート」の2つのエッセイは今でも十分な力をもって訴えかけてきた。その意味での普遍性とでもいうものは失われていない。実は川久保玲氏の受け売りで読んだのだが、すっかりソンタグにはまってしまった。ということでしばらくソンタグを読んでみます。2018/08/12
Fumoh
7
ソンタグ氏の芸術評論集。表題の「反解釈」はその中の論文の一つだが、彼女の批評スタンスを顕わにしていると思われる。おそらく「解釈」とは「作品の無理な意味づけ」を示しているのと、あとは例えば、何にも起こらない映画を「無内容」とやっつけることに対して、警鐘を鳴らしているのではないかと思う。「作品の無理な意味づけ」とは、映画の話になるが、たとえばタルコフスキー映画やフェリーニ映画のレビューでよく見る象徴的意味の解釈だろう。ただ、どこまでが「的確な読み」であり、どこまでが「勝手な意味づけ」なのかというと難しい。2023/10/28
∃.狂茶党
5
誤訳ありB級映画などのタイトルが、邦題と合致しないとか、だけ調べる作業をしていないことを表しており、そのほかの文章に対す信頼度も大きく損なう。文庫化にあたってそのような手直しを求めなかった、ちくま学芸文庫の怠惰は、責められるべきものだろう。 表題作は思いのほか短く、スッキリした文章で、全てに合意するわけでもないが、大変かっこいい。作品を言葉で斬るとはこのようなことだろうと思う。中にはもはや過去のものとなった事柄に対しての、みずみずしい感想、分析が含まれている。 かっこいいって大事だよね。2021/05/11
-
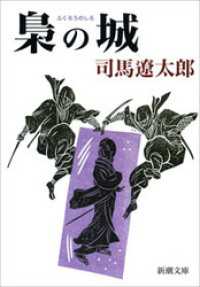
- 電子書籍
- 梟の城 新潮文庫