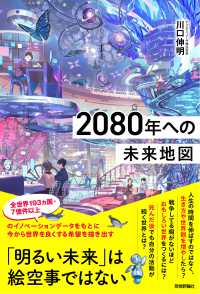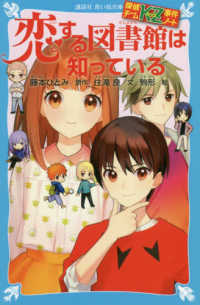内容説明
「わたし」の意識はわたしが知らずにいる無意識によって規定されている。「意識」には「無意識」を、「理性」には「リビドー」を対置して、デカルト以来のヨーロッパ近代合理主義に疑問符をつきつけたフロイト。「自我」(「わたし」)を「意識」「前意識」「無意識」という構造として理解しようとした初期の論文から、それを巨大な「エス」の一部ととらえつつ「超自我」の概念を採用した後期の論文まで、フロイト「自我論」の思想的変遷を跡づけた。「欲動とその運命」「抑圧」「子供が叩かれる」『快感原則の彼岸』『自我とエス』「マゾヒズムの経済論的問題」「否定」「マジック・メモについてのノート」の8編を、新訳でおくる。
目次
欲動とその運命
抑圧
子供が叩かれる
快感原則の彼岸
自我とエス
マゾヒズムの経済論的問題
否定
マジック・メモについてのノート
1 ~ 1件/全1件