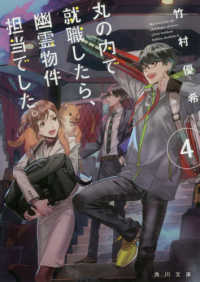内容説明
なにげない英文「書き換え」の奥に潜む人間の認知の営みの深い意味。
目次
1 「文法」の限界
2 「意味」と「文法」
3 「テクスト」と「文法」
4 「テクスト」と「レトリック」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たか
4
いろいろ書いてあるけどSVOO構文と無生物主語あたりが興味深い。レトリックについての記述はやや難解に感じた。2022/02/22
ぽっか
3
今でも中学校では5文型を教えるんだろうか。実は5文型はとても古い概念で、1904年に発表された論文がもとになっているらしい。当時は何も疑いもしなかったけど、よく考えてみればあれは一体何だったんだ.......。かといって、<形式>が変われば<意味>もかわるというテーゼのもと、たとえばto不定詞の選択に反映される認知的意味!みたいなことを教えて、実際に教育効果があるんだろうか。言語に興味があれば、個々の現象もすごく面白いんだけど。2021/04/21
kinkswho
1
初版は30年近く前に発売された本だが、近年の参考書のように平易な文章で書かれていて読みやすい。 中学時代に授業でやったto不定詞節とthat節の英文書き換えを懐かしく思い出しながら、 決して同じ意味の文章を並べ替えていたわけではない事を知る事できて良かった。 さらに高校時代に英文法で習った5文型の中に副詞句が排除されている事を常々疑問に思っていたので 本書を読んで100年程前の理論である事を知り、さもありなんと思った次第。 最新の研究成果がアップデートされずに生き残るのは学校教育に限らずよくある事である。2020/07/08
kaorun_109
1
かつて課題図書として読み、英語学ってなんて面白いんだ!と衝撃を受けた池上先生の著書。再読すると以前のような驚きには欠けるが、忘れていた内容も多かったためかやはり言語学は生き物だし興味は尽きないと改めて思った。2013/11/06
chichichi
0
文の形が変われば意味もかわるはず、そしてそこには何か理由があるはずという認知言語学の営み。既知のtheとthat節の類似性は全く知らなかった。2017/07/24
-

- 電子書籍
- 赤龍の勇者が善人とは限らない【タテヨミ…