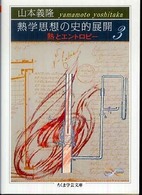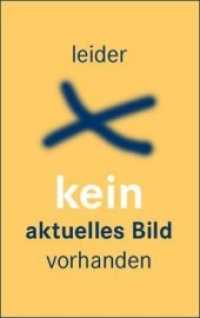出版社内容情報
爵禄を世襲する家柄で諸侯のたぐい、そのはげしい興亡と盛衰を述べる。全三十巻。第一「呉太伯」から「斉太公」「魯周公」、第十三「趙」まで。
内容説明
中国の古典中の古典ともいうべき『史記』の全訳。「世家(せいか)」とは爵禄を世襲する家柄で、諸侯のたぐいをいう。そのはげしい盛衰と興亡を描く。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かごむし
24
世家からは面白くなると聞いていたので、過剰な期待を込めて読み始めたが、面白かった。気がつけば没頭していた。日本人は昔から、史記その他からいろんな故事を引用し、ことわざなんかにしている。それを現代に使うのはちょっと古くておじさんくさいななんて思っていたし、昔は教養と言えば、とりあえず漢文だったんだから、今ことさらに使う必要はないねなんて思っていた。今回史記を読んでみて、文章が持つ強さと瑞々しさに圧倒された。「ほら!例えて言えば・・・史記で言うあの話し!」っていう感じで、定着して行ったんだろうなあと思った。2016/05/13
Francis
11
「世家」は春秋戦国時代、中国の各地に興り、最後は秦に滅ぼされた国を扱う。司馬遷はこれらの王国がなぜ興り、そして滅んだのか、法則性あるいは教訓を見出そうとしているようである。孔子、縦横家の蘇秦、張儀が出てくるあたりは流石は諸子百家の時代と言うべきか。2025/04/08
roughfractus02
7
王(本紀)、臣下(表)の歴史に続く世家は諸侯(王家)の歴史だが、それらが系譜でまとめられると群像劇と化し、その壮絶な栄枯盛衰が文字を通して劇的に展開する。呉太伯、斉太公、魯周公、燕召公、管蔡、陳杞、衛康叔、宋微子、晋、楚、越王句践、鄭、趙の13世家を収める本巻では、名誉と金を巡る裏切り、怨恨、復讐の渦巻く諸侯の殺戮の繰り返しが各々の国の興亡に重なって、勇猛さと愚かさを混交させながら明滅し、そして消える。その傍で国家の興亡に法則があるのを指し示すかのように先行する歴史書『春秋』を表した孔子の存在が記される。2025/11/21
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
7
春秋・戦国時代。ひたすら武力討伐と政治亡命と国君の首の挿げ替えと謀反と内政干渉という無味乾燥な記事が続き退屈。しかし合間にある挿話目当てに読み続ける。岩波文庫が何故列伝のみなのかが分かる。 箕氏の話が出てきて、箕氏朝鮮の逸話が載っていた。伝説的ではあるが文献で確認するとそうした意識があることが分かる。分かりにくくしているのは国君の諡(おくりな)。武・文・霊・哀・献・成・昭・宣・恵・繆・景・荘…こうした文字が王・公・候・伯・子につけて呼ばれるが、それらが被りまくりで誰が誰なのか混乱しそうだ。→続く2021/10/15
ヨクト
5
戦国時代の諸国についての歴史だが、ひとつひとつがなかなかのボリュームがある。ひとつの国を多面的に見られるので、そこの書き方は司馬遷の筆力たるものだろうか。2019/03/07
-
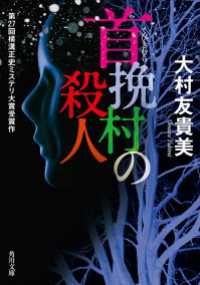
- 電子書籍
- 首挽村の殺人 角川文庫