内容説明
ホメーロス(『オデュッセイア』)にはじまってヴァージニア・ウルフ(『灯台へ』)にいたる三千年におよぶヨーロッパの文学作品。この豊饒な流れから具体的なテクストをえらび、文体美学の分析批評方法を駆使しながら現実模写・描写―、ミメーシスを追求する。全二十章のうち、本巻ではホメーロスからラ・サールまでの十章を収録。
目次
第1章 オデュッセウスの傷痕
第2章 フォルトゥナタ
第3章 ペトルス・ウァルウォメレスの逮捕
第4章 シカリウスとクラムネシンドゥス
第5章 ロランがフランク勢の殿軍に推挙された次第
第6章 宮廷騎士の出立
第7章 アダムとエヴァ
第8章 ファリナータとカヴァルカンテ
第9章 修道士アルベルト
第10章 シャステルの奥方
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
10
固定した人と作品でなく、流動する集団と文体から文学をネットワークするとハブ=作品が現れる。古代ギリシャと聖書に始まる文学はキリスト教徒の十字軍遠征と共に騎士道物語を、疫病の蔓延と共に巡礼物語を生む。同時に、予兆と顕現を非時間的に照応させる「比喩形象」的現実(アダムの肋骨からイヴが生まれる逸話は処刑されるイエスの脇腹に刺さる槍に顕現する)は崩れ、鳥瞰描写は出来事描写に変わる。本書ではギリシャの異教的知が移動して地方語で書かれる『神曲』と疫病後の移動を出来事的に描く『デカメロン』がルネサンス以前のハブとなる。2020/02/07
H2A
9
ずっと前に読んだのに、時間が経つとまるで初めて読む本であった。アウエルバッハ同書の文章は固くクセがあり、しかも訳文も直訳調なのだがそこがかえって独自の味がある。そろそろ新訳出ても良さそうだが、この本の内容の深さ、巨大さ、鋭さ、どれをとっても圧倒される。上巻はホメロスからラサールまで。以前読んだ時には前半斜め読みだったろうか。思わぬ新鮮な驚きがあった。文学好きなら必読と思う。2025/09/25
Z
3
リアリズムが誕生するか、という時点までのヨーロッパ文学史。ギリシアとキリスト教を軸に文学史をみるが、キリスト教の文学にもたらした遺産として比喩形象という概念はすごく魅力的だった。時間軸の任意の二点を選び出して、垂直的あるいは超越的な意味をもたらす技巧とでもいえばいいだろうか。私にとって文学的という感性を見事に表している概念が書かれていて、読んでいて興奮した。幅広い時代をしょうりょうしており、偉大なるヨーロッパ知性を見れる。下巻はどうなるか?2015/04/07
tieckP(ティークP)
3
ヨーロッパ文学を古代から近代まで辿り、文体と歴史の関係をたどる名著『ミメーシス』。定番でありながら、なかなか読み進められず、おそらく三度目くらいにようやく上巻を読み終える。前半はともかく、中盤から後半は、知らない作品の多さと歴史知識の不足で、まだまだ理解できたとは言いがたい。おそらくキリスト教文学と、ギリシャの文学、それにラテンあたりの修辞全盛の文学がどこまでも影響をもたらしたのだと思う。文体論だけに、それを翻訳でやるのに必要な文体の訳し分けが見事になされていて、その偉業には感心した。2014/08/03
misui
2
「(…)歴史の中におかれた個としての人間の、神の秩序にもとづく不滅性は、まさしく神の秩序に抗う転回をなしとげ、この秩序を自らに奉仕させその光を奪ってしまうのである。人間の姿が神の姿の前に出現する。ダンテの作品は人間のキリスト教的・比喩形象的本質を実現しながら、その実現のうちにそれを破壊してしまう。強固な枠組みは、それが包括する形象のあまりな豊かさに圧倒されて砕け散った。2021/04/09
-
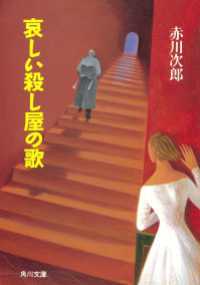
- 電子書籍
- 哀しい殺し屋の歌 角川文庫








