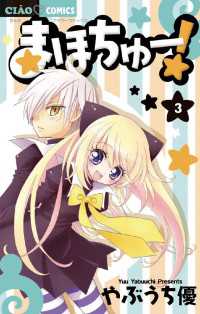内容説明
哲学とは自分を深く知るための、他者とほんとうに関わるための、もっともすぐれた技術(アート)なのだ。哲学の読みどころをきわめて親切に平易に、とても大胆に元気にとらえなおした斬新な入門書。もちろんプラトンもデカルトもカントもヘーゲルもニーチェもフッサールもハイデガーも大物はみな登場。この一冊で哲学がはじめてわかる。
目次
第1章 哲学“平らげ”研究会(哲学を「平らげる」;哲学、自分を知る技術;“耳学問”のすすめ)
第2章 わたしの哲学入門(哲学とは何であるか;わたしの現象学―フロイト対フッサール;青年期的“独我論”;独我論をいかに破るか;ロマンとリアル;現象学の発見;ほんとう、よしあし、美醜)
第3章 ギリシャ哲学の思考(初期ギリシャの哲学者たち;デモクリトス―ソクラテス;プラトンとアリストテレス)
第4章 近代哲学の道(デカルトとスピノザ;カント、近代哲学のチャンピオン)
第5章 近代哲学の新しい展開(現象学;キルケゴール、ニーチェ;ハイデガーと自己了解)
終章 現代社会と哲学(現代思想のアポリア;現代思想を起えて)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
特盛
35
評価3.9/5。ヘーゲルの精神現象学解説本でお世話になった竹田先生の、30年以上前の哲学入門書。フッサールの現象学推しの先生ならでは語り。哲学は、自分の頭でものを考える、困った時に助けられる、自身の存在の了解、という意義を持つと著者は言う。存在の了解とはつまるところ、現代がある意味置き去りにしている、真善美=エロス(世界に引き付けられる働き)に向き合うこと。でないとニヒリズムやペシミズムに陥るよと。自身が哲学に入り込んだ学生時代の経緯、西先生との繋がりもヘーゲル本共著の背景はそんなだったのかと面白かった2025/03/24
KAKAPO
21
著者と哲学との出会いのプロセスが書かれており、著者と似たような状況に置かれている読者にとって最も理解しやすいものだ。哲学と言うと、古代から始まる哲学史を学ぶことだと思っている方も少なくないと思うが、著者によると、哲学とは、①ものごとを自分で考える技術。②困ったとき、苦しいときに役に立つ。③世界の何であるかを理解する方法ではなく、自分が何であるかを了解する方法。とのことだ、苦しい時、自分が何であるかわからなくなってしまった時、この本を手に取ると、何らかの答えを見つけることができるかもしれない。1210142012/10/14
けやき
19
【再読】2020/10/11
俊
18
前半は著者が経験から得た哲学観を語り、後半は著名な哲学者達の思想を平易に紹介した本。哲学入門というタイトル通り、哲学の難しい事柄を非常に丁寧に、噛み砕いて説明している。それでも難解だけれど(笑)。ほんとう(真理)は存在せず、主観と主観の相互了解によって「妥当」を導く。何となく大意は掴めても、具体的な事象に置き換えようとするとたちまち躓く。難しい、本当に難しい、でもどこか引き付けられる哲学の不思議。良書。2014/06/03
ふね
14
哲学に興味を持ったので、入門っぽい本書に手を出してみた。たしかに初学者向けというか、哲学を易しく説明しようという筆者の努力が感じられる1冊だった。ただしさらさらと読んでしまうと忽ち取り残されてしまうのが哲学の難しいところ。頭を働かせられた読書だった。今度は原書に挑戦したい。2015/02/21



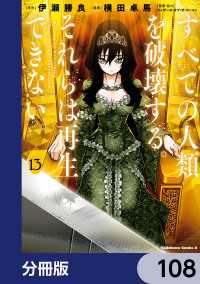

![中医臨床[電子復刻版]通巻4号](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1031292.jpg)