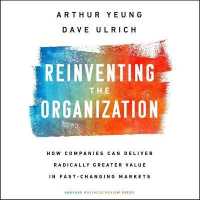内容説明
天然の水鏡、銅鏡、そしてガラスの鏡―。すべてを容れる鏡は、古今東西の人間の心にどのような光と迷宮とをもたらしてきたか。ギリシア、中国、日本では…。仏教では…。レヴィ・ストロース、ボルヘス、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ルイス・キャロス、李白、釈迢空は…。鏡面の多彩なきめらきを写しとりながら、テオーリア(観照)はつづく。
目次
第1部 鏡のテオーリア(歩む鏡;向きあった鏡;見ることは見られること;まなざし;見ることは驚くこと ほか)
第2部 鏡をめぐる断章(眼の月;アルキメデスの凹面鏡;バックミラー考;灼きつく影;世界の鏡 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
67
古来、鏡はものを写す道具である以上にある種の象徴であった。という事を古今の文献から紐解いていく一冊。著者の博学と文才はもちろんながら、それらがだんだんと鏡という物に対しての人々の心性を紡ぎだしていく様は読んでいて酔うばかり。西洋の鏡から月を写す水鏡、八咫鏡から仏教の大円境地、インドラの網まで、アルキメデスの鏡から李白等鏡を詠んだ漢詩まで、洋の東西時代の前後を問わず鏡に対する智を集積させていく様はやはり澁澤龍彦を思わせるなあ。本書の推薦も彼だし。鏡が人を写すのか、人が鏡を写すのか、まさにテオーリア。2024/01/04
あ げ こ
11
鏡というものの呪力や迷宮性、驚きを媒介にしてまなざしと、輝きを通じて太陽とさえ結び付くこと。〈おびただしい鏡の反射し合う光の渦〉のあまりにも鮮烈な光景。眼の抱く欲望の、或いはもたらされる愉悦と恐怖の無際限さ。天上と冥府とを結ぶ通路としてのそれ。水晶球の幻想的なきらめき。そして水鏡と月という極致めいた美しさまで…。数多ある魅惑の痕跡の内より詩人がすくい上げ、その言葉によって結ぶイメージはいずれも美しく、けれど水鏡と月こそが、何よりも誘惑的であるように感じられる。鏡が水の性をそなえていることの疑いようのなさ。2022/10/23
三柴ゆよし
6
「観念された鏡とは、つまるところ、増殖と反復とを基本原理とする一個の宇宙であって、この世界に正確に対応する言語はおそらく果てしない類語反復に他ならないであろう。鏡は一個の無限宇宙なのだ」。曇りのない文章で紡がれた、本書自体あたかも鏡のごとき書物であった。古今東西の文献を逍遥しながら展開される著者の思考はきわめて明快。澁澤龍彦や中野美代子よりもボルヘス的だが、決して晦渋ではない。絶版であることが惜しまれる好著。2010/12/11
ふゆきち
1
プリミティブなところから始まり仏教哲学にまで至る第一部と、アラカルトな第二部。200ページそこそこながら読み応えがありました。2022/10/08
-

- 洋書電子書籍
- The Pasta Book : Re…
-

- DVD
- ロルナの祈り