出版社内容情報
人生のリズムを整える。一生モノの「気づき」がある! 美術館に行きたいけど行けていないあなたへ。タイパ志向のご時世、忙しいあなたにこそ、至福の余白時間を美術館で過ごすことが人生に必要なのです。効果は分かりやすくはないですが、美術館を出た後、世界が違って見えるはずです。時間がなくても、知識がなくても、大丈夫。とある現役学芸員が、美術館での過ごし方のキモとコツを、最新の美術館事情とともにガイドします。「語れる」ための鑑賞の心得も、レクチャーしますよ。さあ、スマホから顔を上げて、出かけましょう。 第1章 タイパの真逆にある美術館(「時間はあるのに行けない」はなぜ;「美術=ビジネスマンに必須の教養」ブーム;コスパ・タイパの呪縛;余裕のある時代は美術、余裕のない時代は技術;普段から美術館に行く人はどこが違う?) ちいさな美術館の学芸員[チイサナビジュツカンノガクゲイイン]
好評既刊『学芸員しか知らない 美術館が楽しくなる話』
『学芸員が教える 日本美術が楽しくなる話』(いずれも産業編集センター刊)
著者の現役学芸員=人気noteライターによる
ユーモア溢れる美術館ガイド
「美術館に行く意味って何ですか?」に全力で回答!
タイパ志向のご時世こそ人生に至福の余白を。
センスを充電できるコツ、美術館での過ごし方の秘訣を教えます。
美術館に行きたいけど行けていないあなたへ。
忙しいあなたにこそ、至福の余白時間を美術館で過ごすことが人生に必要なのです。美術館を出た後、世界が違って見えるはずです。
時間がなくても、知識がなくても、大丈夫。
とある現役学芸員が、美術館での過ごし方のキモとコツを、最新の美術館事情とともにガイドします。
「語れる」ための鑑賞の心得も、レクチャーしますよ。
さあ、スマホから顔を上げて、出かけましょう。
【目次】
はじめに 美術館に行きたいけどなぜか行けないあなたへ
第1章 タイパの真逆にある美術館
1 「時間はあるのに行けない」はなぜ
あなたが美術館に行けない理由は本当に時間が無いから?/余暇時間は増加傾向なのに/時間があっても美術館に行かない・行けない/二極化する来館者/子育て世代と美術館のニーズは一致している/「透明化」してしまった現役世代
2 「美術=ビジネスマンに必須の教養」ブーム
「美術は役に立つ」系書籍の流行/ロジカル・シンキングの次のアート・シンキング/「すぐ分かる」系書籍で埋まる書店棚
3 コスパ・タイパの呪縛
何もしていない時間は居心地が悪い/「可処分時間」が追い立てる/タイパの真逆にある美術館/「役に立つ・立たない」の天秤/似て非なる映画鑑賞と美術鑑賞/自発的な行動、してますか?
4 余裕のある時代は美術、余裕のない時代は技術
美術が技術だった幕末、明治/一般庶民まで美術を楽しむ余裕があった江戸時代/現代日本はどちらのフェーズか
5 普段から美術館に行く人はどこが違う?
学芸員は案外動機が分かっていない
第2章 美術鑑賞の変遷
1 最近10年でヒットした展覧会を振り返る
10年間のヒット展覧会ランキング/コロナ禍ビフォーアフター/ヒット展覧会の共通項を分析してみよう/レアなものはやっぱり見たい!―「正倉院展」/消えない海外への憧れ―「オルセー」「ルーヴル」「モネ」……/定番コンテンツという王道の安定感―印象派、琳派、国宝……/大ヒットしない展覧会にも意味がある?
2 展覧会の歴史 ヨーロッパから日本へ
特権階級にのみ許されていた芸術鑑賞/展覧会の誕生はアーティストの誕生/日本初の美術館と展覧会/日本に根付いていく展覧会制度
3 日本の展覧会の黄金時代
高度経済成長期の3大ヒット展/80年代からの「美術の大衆化・日常化」/マスメディア主導のブロックバスター展/デパート展、華やかなりし頃
第3章 美術館の新たな取り組み
1 SNSによって変わる美術館の常識
SNSを有効活用した展覧会の広報/SNSも一発逆転で集客できる魔法のツールではない/シェアを前提とした写真撮影の普及/展示作品の著作権をいかに守るか/著作権法もマイナーチェンジ/撮影許可がはらむ危険性
2 美術館のデジタルシフト
オンライン鑑賞の功罪/鑑賞を一つの体験として考える/没入型展覧会の増加
3 クラウドファンディングをする美術館の苦境内容説明
目次
第2章 美術鑑賞の変遷(最近10年でヒットした展覧会を振り返る;展覧会の歴史 ヨーロッパから日本へ;日本の展覧会の黄金時代)
第3章 美術館の新たな取り組み(SNSによって変わる美術館の常識;美術館のデジタルシフト;クラウドファンディングをする美術館の苦境;四苦八苦のインバウンド対応)
第4章 SNS時代の美術館 鑑賞する側が主役になる(基本的な鑑賞の心得;主体的な鑑賞をするための秘訣はアウトプット;鑑賞メモの力を今こそ伝えたい!;「美術を語れる人」になるためには)
第5章 結局、美術館に行く意味って何?(現代病の処方箋としての美術館;美術鑑賞とマインドフルネス;フォースプレイスとしての美術館)著者等紹介
東京都生まれ。都内のとある美術館で働く学芸員。複数の大学でも教鞭を執る。2022年からnoteにて美術館や学芸員に関する仕事コラムをスタート。すでに投稿した記事は300本以上。現在もコツコツと更新継続中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
-





akky本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nonpono
レモングラス
はっせー
shikashika555
Shun
-
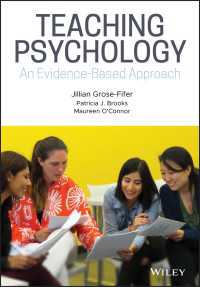
- 洋書電子書籍
-
エビデンスに基づく心理学教育法
…
-
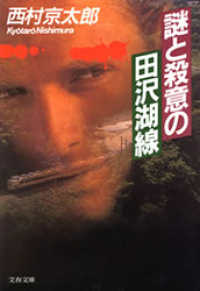
- 電子書籍
- 謎と殺意の田沢湖線 文春文庫






